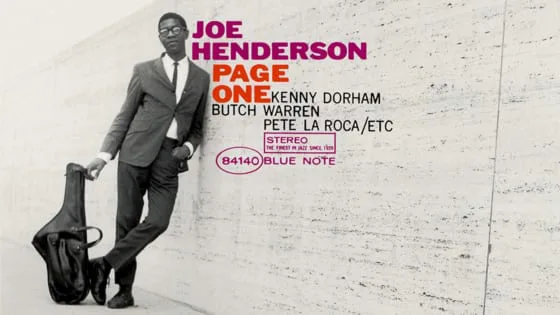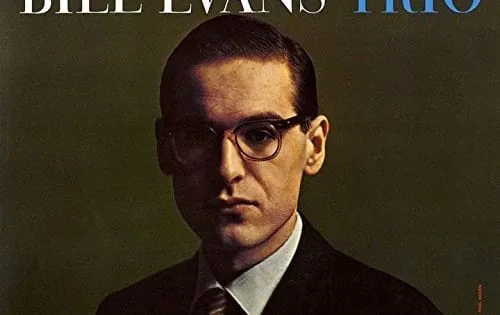投稿日 : 2018.01.16 更新日 : 2021.01.25
セロニアス・モンクが愛した帽子【ジャズマンのファッション/第6回】
取材・文/川瀬拓郎

MENU
現在のハリウッドスターやポップスターがそうであるように、かつてジャズマンはファッションリーダーだった。そんな彼らのファッションを、音楽とともに考察していきたい。
帽子好きのミュージシャンたち
2017年末に、イタリアの老舗ハットメーカーであるボルサリーノが、倒産の危機というニュースが入った。どうにか資金援助を得て、ブランド存続の見通しが立ったようだが、今後の再建も一筋縄ではいかないという。ソフト帽の代名詞的ブランドであるボルサリーノが無くなってしまったら、クラシックスタイルを信条とする世のダンディはもちろん、多くのファッション好きにとっても、大きな痛手となることは間違いない。
改めて考えてみると、ハットのかっこよさを教えてくれたのは、いつもミュージシャンだった。最近ではツバが長い山高帽を被ったファレル・ウィリアムス。目深に被ったファーハットが衝撃的だったジャミロクワイのジェイ・ケイ。カンゴールのハットでおなじみのランD.M.C.。黒いウエスタンハットで雄叫びを上げるモーターヘッドのレミーなどなど……。個性的な帽子とともに記憶されたミュージシャンは、枚挙にいとまがない。
モダン・ジャズの名盤におけるハットを探してみると、これがまた刺激的で面白い。ポークパイハットでお馴染みのレスター・ヤング。ツバの短いソフト帽を被っていたウィントン・ケリー。その甥であるマーカス・ミラーも大のハット好きとして有名だ。そんな中でも特にハットの達人として挙げるべきは、ソフト帽、ベレー帽、ポークパイ、キャスケット、ハンチング、ニットキャップなどなど、さまざまな帽子を愛用していたセロニアス・モンクだろう。

1963年発表のアルバム『Monk’s Dream』は、モンクのコロンビア・レコード第一弾作品である。ジャケット写真の彼は、リボン付きのフェルトハットをチェックのジャケットに合わせている。瞳を閉じ、なおかつピントの甘い写真を使ったのは、アルバムタイトルの “夢うつつ”感を表現したのだろうか。ミステリアスな雰囲気である。
ブリム(つば)の短い円筒形のこのハットは、ポークパイハット(注1)と呼ばれるもので、額の上にくる正面部分にブローチを付けているのも彼らしい演出なのだろう。ちなみにこのLPは彼の生涯で最も売れた作品となり、リリースの翌年には『TIME』誌(1964年2月28日号)の表紙を飾った。ここでは肖像画が使用されているが、やはり帽子(チロリアンハット)姿だ。
注1:円筒形で天面が平たい形状のハット。その形状が挽肉などを詰めたパイに似ていたことに由来。別名はテレスコープハット。かつてのイギリスでは女性用ハットとして人気だったが1950年代のアメリカで人気が再燃。お決まりの中折れソフト帽に飽き足らぬ洒落者たちが、ポークパイハットを愛用した。

こうした “モンク生前最大のブレイク期”から遡ること6年前。リバーサイドから発表した『Monk’s Music』(1957年)ではハンチングを着用している。なぜかレッドワゴン(注2)に乗って、手には赤い鉛筆。3つボタンのダークスーツにチェックのハンチング、竹製フレームのサングラスと金メッキの腕時計という、小物のチョイスがじつにエキセントリックだ。タイトルなどを手書き風にしたデザインは、完全に後付けによるアイデアだと予想される。スタイリッシュという点では『Monk’s Dream』に軍配が上がるが、彼の音楽性を考えると『Monk’s Music』の奇天烈さもカッコ良く思えてしまう。
注2:幼児用のワゴン。玩具としてではなく荷物の運搬などでも重宝される。ラジオフライヤー社の製品が有名だが、モンクが乗っているのJCペニーが発売した「Rex 90 ジェットワゴン」。

「ステージ上で帽子」の非常識
「思い入れのある帽子を被ることで、自分がいちばん心地いい状態にして、外界の余計な情報を遮断してくれる。モンクにとっての帽子は、自己埋没感を高めるためのカプセルのような存在だったんじゃないかな」
そう語るのは、服飾評論家の出石尚三氏である。1960年代からメンズファッションの道に入り、ウイットに富んだコラムや数々の著作で知られるご意見番。帽子についての造詣も深く、帽子のセレクトショップとして知られるoverrideのHPで連載コラムを執筆しているスペシャリストだ。さらにモンクの心理について、出石氏はこうも語る。
「当時、ステージ上で帽子を被るのはマナー違反だったし、白人ジャズマンは決して帽子を被らなかった。でも、モンクは『白人たちのルールなんて関係ないね、だって俺は黒人だし、アーティストなのだから』と思っていたんじゃないかな。そこには黒人ジャズマンとしての誇りがあったのだろうし、典型的なアイビースタイル(注3)を茶化すような反骨心も感じられる」
注3:アメリカ東部の大学8校(ハーバード、イエール、プリンストン、コロンビア、ペンシルバニア、ブラウン、ダートマス、コーネル)の学生たちに象徴されるファッション。同8校によるフットボール連盟「アイビーリーグ」に由来。

そもそも戦前のヨーロッパやアメリカ、そして日本でも、紳士が外出するときは帽子を被るのが当たり前だった。室内に入れば脱帽するという厳格なルールがあり、特に東部アメリカの白人男性は、公私においてマナーにうるさかった。こうした様式やマナーが、アイビースタイルの根本にあるのだ。
「アイビーとは良家の子息で真のエリートであることを証明する着こなし。名門校に進学した彼らは、必ずイギリスに留学して、徹底的に英国流の着こなしやエチケットを叩き込まれ、喋り方まで英国式になるんです。ところが、そんな状態でアメリカに戻ってくると、あまりに“ええかっこしい”なので周囲から浮いて見える。そこで彼らは、ちょっとした照れ隠しというか独自の工夫をした。たとえば、糊の効いたハイカラーのシャツではなくボタンダウンシャツ。ジャケットは英国的なスクエアショルダーではなく、丸みのあるナチュラルショルダー。これを3つボタンの“上2つがけ(英国式)”ではなく、3つボタンの“中ひとつ掛け”にした」(出石氏)
そんなアイビー(白人エリート層)と対極にあった50〜60年代半ばの黒人ジャズマンたちが、アイビーを独自解釈した結果として「ジャイビー・アイビー」というスタイルが生まれたという。
「ビートニクがそうであったように、彼らはいつも“埒外”な存在。白人の常識に囚われず、自由な着こなしを体現し、20年後には当たり前になるスタイルを彼らは予見していたのです。今でこそミュージシャンがステージ上で帽子を被るのは当たり前のことですが、モンクは半世紀以上も前から実践していたのですね」(出石氏)

キャリア初期はたっぷりとしたドレープスーツを着用し、50年代はチェックやストライプのスーツ。60年代以降は自らのルーツに立ち返るかのように、アフリカの民族衣装のような服を着用していたモンク。そして必ずインパクトのあるハットかキャップを合わせて、独特な存在感を放っていた。それにしても、戦後のアメリカでこれほど多様な帽子を手にすることができたのだろうか?
「じつは50年代のアメリカは世界一のファッション輸入国でした。多くの女性が、パリで流行していた服を我先にと買い求め、何百万円もするようなディオールのドレスが飛ぶように売れました。一方、裕福な男性はみなサヴィル・ロウ(注4)で仕立てたスーツを着ていました。帽子も主にヨーロッパから輸入して、デパートで販売していたのです」(出石氏)
注4:ロンドンのメイフェアにあるショッピング街。オーダーメイドの紳士服店が数多く立ち並ぶ。日本語の「背広」の語源であるという説も。
やがて訪れる“無帽”時代
ところが、第二次大戦が終わると多くの男たちが帽子を被ることをやめてしまう。明確な理由がそこにあったわけではないが、出石氏はこう分析する。
「やっぱり、もう軍帽は嫌だ!という気分だったんでしょう。戦時における帽子は、軍属や階級を象徴するものでしたから。特に大量の物的・人的資源を戦争に投じたアメリカ人はその傾向が強かった」
そんなアメリカ人の気分は、欧州にも伝播する。
「ナチス占領下のパリを解放したのはアメリカ軍でした。映画『欲望という名の電車』に登場するマーロン・ブランドは、白いTシャツとジーンズを着ていますが、じつは戦争帰りの男であるということを暗示しているのですね。こうしたアメリカ帰還兵の着こなしがパリの若者にも受け入れられ、ジーンズは世界中で憧れの対象となったのです。戦勝国の中で、政治的・文化的にも多大な影響力を持つようになったアメリカ人が帽子を脱いだことが、ヨーロッパにも影響して“無帽”時代が幕を開けるのです」(出石氏)
こうして多くのアメリカ白人男性が帽子を被らなくなった中で、あえてモンクはステージで帽子を被り、頻繁にその種類を変えていった。白人に対するアンチという意味もあるのかもしれないが、とにかくモンクは風変わりな帽子に目がなかった。アメリカ国内はもちろん、巡業したパリやロンドンでも新たな帽子を手にしたのだろう。他の多くのジャズマンは、気に入った型のハットを変えることなく愛用し続けてトレードマークとするのが常だが、モンクのように頻繁に帽子を変えるのは珍しい。

「モンクの個性的な帽子姿もそうですが、当時の常識から逸脱していたジャズマンの着こなしが自然に思えるのは、そこにリアリティがあったからではないでしょうか? 自分の進むべき道が見えている人には、それが外見上のファッションとしても現れる。その人の暮らし方や必然性があってこそ、着ている服が本物に見える。そうした意味でも、一見風変わりな帽子も違和感なく似合うのは、モンク自身の内面性と深く関わっていたからでしょう」(出石氏)
モンク生誕100年という節目
70年代以降にシーンから遠のき、1982年にこの世を去ったモンク。そのユニークな音楽性が高く評価されるのは、死後になってからである。モンク生誕100周年となる昨年は、『セロニアス・モンク モダン・ジャズの高僧』(河出書房新社)、『セロニアス・モンク 独創のジャズ物語』(シンコーミュージック)などの出版物や、初期作を収めたボックスセットなど、モンクの当たり年となった。
極端に無口で超然とした態度、数々の奇行でも知られるモンク。数々の評論家や関係者が語る、晩年の精神疾患などについての研究を読んでみても、本当のところはよく分からない。村上春樹のエッセイ『セロニアス・モンクのいた風景』(新潮社)にもある通り、ずっと“謎の男”のままだ。あのハットはどこのブランドのもので、どういう意図があったのかと詮索するよりも、在りし日の帽子姿を目にしながら、遺された音楽に耳を傾けるだけでいいのだろう。
【取材協力】
出石尚三
1944(昭和19)年、香川県生まれ。服飾評論家、ファッション・エッセイスト、ウォッチオブザイヤー審査委員長。1960年代にファッションの道へ入り、以後メンズ・ファッション一筋に活躍。著書に『男のお洒落』、『ロレックスの秘密』、『帽子の文化史』など。
override
ルーツは1920年代に帽子卸として創業した栗原商店。帽子のセレクトショップとして、1999年に原宿・キャットストリートに第一号店をオープン。以後全国に50店舗以上を展開し、オリジナル商品の製造・販売、様々なブランドやアーティストとのコラボレーションなども積極的に手がけている。