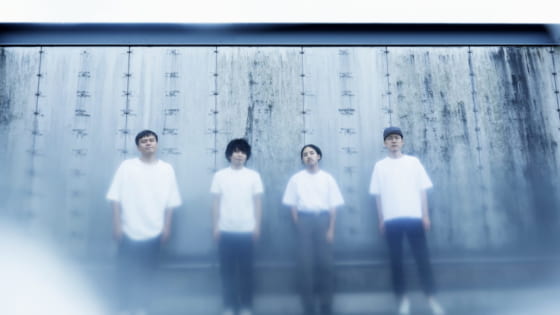投稿日 : 2019.05.17
【Kan Sano】新旧ソウルを消化吸収したニューアルバム完成「今まででいちばん個人的な作品になりました」
取材・文/林 剛 写真/山下直輝

MENU
Kan Sanoがアルバムをリリースするのは『k is s』(2016年)以来2年半ぶりのことだ。
本人名義としては4作目となる『Ghost Notes』は、ピアノ/キーボードを中心に、ドラム、ベース、ギター、トランペットなどの楽器をマルチに操る彼が、作詞・作曲、ヴォーカル、ミックスに至るまでオール自作自演で仕上げたアルバム。
なお、本作の初回限定盤には、カヴァー作品集『pf_soul_01-08』が付帯され、ディアンジェロやマーヴィン・ゲイ、ビル・ウィザーズ、ミシェル・ンデゲオチェロ、サム・クックといった、ソウル/R&Bの名曲をピアノ独奏。アルバム本編でも、そうした音楽に触れてきた過去と向き合いながら、新しいソウルを奏でている。
新旧ソウルのエッセンス
──これは個人的な解釈ですが、ファーストアルバムの『Fantastic Farewell』(2011年)は “ビート・メイカーとしてのKan Sano”が際立った作品だったと思います。
「はい、そうですよね」
──次いで、セカンド『2.0.1.1』(2014年)はピアニストとしての存在感が強いアルバム。そしてサードアルバム『k is s』(2016年)は、ポップ・メイカーとしての側面がフォーカスされた印象です。ちなみに今作は、それらとはまた違ったアプローチですよね?
「ひとつの作品を作ると、次は違うことをやってみたくなるんです。前作は打ち込みメインでアップ・テンポの曲が多くて、シンガーもたくさん招きました。だから今回は、生楽器主体で、自分ひとりだけで作ってみよう、と」

──そこは大きな特徴ですよね。すべてのパートを自分で担当している。
「あと、もうひとつ。10代から20代前半の頃に聴いていたネオ・ソウルや(古い)ソウル・ミュージックを、これまで自分のサウンドとしてうまくアウトプットできていなかった。でも今なら、それができるかなと思って。過去の作品でもそういうアプローチは多少あったのですが、今回はもっとダイレクトにやってみたいなと」
──冒頭の「End」からして典型的なネオ・ソウルですけど、ソウルクエリアンズ(注1)を中心としたネオ・ソウルのムーヴメントが起こったのはSanoさんがバークリー音楽大学に行かれた2000年前後のことですよね。ちなみに当時 “ネオ・ソウル”という言葉は、クエストラヴ(注2)のような当事者たちの間では煙たがられていましたけど。
「はい。まあ、便宜上 “ネオ・ソウル” と呼んでいた90年代後半から00年代前半のソウルですよね。ディアンジェロ、あとエイドリアナ・エヴァンスのファーストもかなり聴いていました」
注1:90年代の半ばに形成された、ミュージシャン/プロデューサーの集団。グループ名(Soulquarians)の由来は、中心メンバーであったクエストラブ、ディアンジェロ、ジェイムズ・ポイザー、J・ディラの4者が全員、みずがめ座(Aquarius)であったことから。
注2:米ヒップホップグループ「ザ・ルーツ」のドラマー。ディアンジェロ、エリカ・バドゥ、エイミー・ワインハウス、ジョン・レジェンドなどの作品プロデュースなどでも知られる。

──今回、限定盤付属の作品集『pf_soul_01-08』ではエイドリアナの「Seein’ Is Believing」をカヴァーしていますが、本編の「Ride On The Back To Back」もエイドリアナ風というか、エイドリアナの曲を手掛けた、旦那のドレッド・スコット的なプロダクションを連想しました。
「モロですよね(笑)。影響を受けたのはビート感とギターの使い方です。ロニー・ジョーダンのような、ジャズ・ギタリストのサウンドをサンプリングしたみたいな感覚を取り入れたくて」
埋められない溝もある…だからこそ
──“何々風”という喩えは安直かもしれませんが、とはいえ、今回のアルバムはストレートに “好きな音楽のエッセンス” を抽出したものになっているわけですね。
「具体的な曲までは意識していないですが、そういう音楽をたくさん聴いてきた蓄積があって、それがいま、自分のものになって出てきているというか。例えばディアンジェロの『Voodoo』のビート感とかベースのモタり方とかは、自分のボキャブラリーとして出来上がっているので、自然に出せたのかなと」
──そのアウトプットが、今だった。
「はい。10年以上経ってようやく具現化できたというか。20代の頃は今ほど演奏に自信がなくて、自分で弾いたものを一度サンプリングして加工したりとか、トラックメイカー的な視点で自分の演奏を料理していました。でも30代になってそれなりに自信もついてきて、もう少し素直に自分ができることを曝け出してもいいんじゃないかと思いまして」

「あと、前作ではポジティブな気持ちが強くて、そういう気持ちこそが世の中との接点になると思っていたのですが、ここ数年、音楽シーンや社会の動きを見ていても、世間と自分との間に溝があるというか、埋められない距離が年々大きくなっているという実感があって。だったら今やりたいことに専念しようと。結果的に今まででいちばん “個人的な作品” になりました」
──しかも今回はすべて自作自演。先行シングルの「DT pt.2」は、ジェイコブ・コリアーみたいに楽器の音をルーパーで重ねていくパフォーマンス動画も公開されていましたが、あんな感じで?
「まさしくあんな感じですね。録音から作詞、作曲、ミックス、全部ひとりでやったので。特に自分はドラムに対するこだわりが強くて、今回の曲もドラムから録り始めて、ドラムを納得いくものにするところから始めました」
「〈DT pt.2〉に関しては、ライブで披露していた〈DOWNTOWN〉という曲の “パート2”という意味で、〈DOWNTOWN〉のワンフレーズを歌ったボーカルをサンプリングして声ネタとして使い、フェンダーローズで遊んでみようと思ったんです」
──「Horns Break」という曲もありますが、今回感じたのはトランペットの緩く浮遊する感じがロイ・ハーグローヴっぽいなと。
「そうですね。昔からRHファクター(注3)を聴き込んでいたので、今回はそれを素直に出そうと。当時流行っていたネオ・ソウルにジャズ・サイドからアプローチしていったのがロイ・ハーグローヴで、自分のスタンスと近いですし。70年代のドナルド・バードなんかの影響もありますけどね」
注3:米テキサス州出身のトランペット奏者、ロイ・ハーグローヴ(2018年11月に逝去)が2003年に発足したプロジェクト。同名義で3作のアルバムを発表。
──ここまでホーンが目立つSanoさんの作品も珍しいですよね。
「アルバムでホーンを使ったのは、じつはほぼ初めてのことで、高校時代に吹奏楽部で吹いていたトランペットを久々に引っ張り出してきまして。ヘタウマな感じも若干あるんですけど、思い切ってやってみました」
“ネオ・ソウル”の成分分析
──『pf_soul_01-08』(限定盤付属の作品集)ではアンソニー・ハミルトンの「Lucille」を取り上げていますが、彼もRHファクターに参加していましたよね。
「じつはRHファクターの曲もカヴァーしようと思っていたんですよ。アルバムの制作中にハーグローヴが亡くなったんですよね…」
──Pファンクのネオ・ソウル解釈みたいな「Don’t You Know The Feeling?」を聴くと、以前レジー・Bの2013年作『DNA』(収録の“Love’s The Way”)でコラボしていたSanoさんを思い浮かべました。
「今の事務所(origami PRODUCTIONS)に所属する前にSoundCloudで海外アーティストやDJと毎日絡んでいて、その中にレジー・B(注4)がいたんです。レジー・Bの曲は僕が作ったトラックに歌を乗せたんだと思います。〈Don’t You Know The Feeling?〉は、RHファクターにも通じるPファンクっぽいニュアンスが欲しくてシンセベースを入れました」
注4:Reggie B/米カンザスシティ出身のマルチ・クリエイター/シンガー。ファンクやジャズ、ネオ・ソウルなどを包括したハイブリッドなフューチャー・サウンドを標榜。Tokyo Dawn Recordsなどからリーダー作をリリースしている。

──そもそもネオ・ソウルって、Pファンク、プリンス、シャーデーの成分が含まれていますよね。あと、『pf_soul_01-08』(限定盤付属の作品集)で「Running Away」を取り上げているスライ&ザ・ファミリー・ストーンも。
「まさにそうですね。特にスライの『暴動』はひとりで宅録したような密室感が好きで。あのアルバムってディアンジェロの『Voodoo』の大本になっていると思うんですけど、今回僕もひとりで作ったので同じ匂いが出ているのかなと。温度低めのファンクっていうか」
──インストのスロウ「1140」にもそんな印象を受けます。
「タイトルの “1140” は、バークリー音大のビル(ストリート)の名前。そこは僕にとっての青春の場所なんです。バークリーではmonolog(注5)とバンドをやっていまして、DJ文化というか、ヒップホップ視点でのジャズみたいなところはmonologに教えてもらった部分が大きいんですよ。当時はブロークンビーツも流行っていて、影響を受けました。ジャザノヴァにも共感してましたね」
注5:米ボストンを拠点に活動する日本人プロデューサー/マルチ楽器奏者、金坂征広のプロジェクト・ネーム。故ジョージ・デュークやパトリース・ラッシェンなどとも共演し、自身のリーダー作も発表している。Kan Sanoと同時期に、バークリー音楽大に在学。
──今回のアルバムだと「My Girl」がそういう匂いを発しています。
「ヒップホップの人がやる四つ打ちというイメージで、いわゆるハウスのようなアップ・テンポではないですが、わりとノリやすいヒップホップのビートですね」
ゴースト・ノートの奏功
──リリックに “走り出すベースライン” という文言が出てきたり、歌詞の中からいくつかの音楽用語が聞こえてきますが、そもそも『Ghost Notes』というアルバムタイトルも音楽用語ですよね?
「そうです。ゴースト・ノートって昔から好きな言葉で、バーナード・パーディのドラム・レッスン動画の中でもゴースト・ノートについて語られていて、以来、演奏するときはいつも意識しています。あと、ちょっと日本っぽいニュアンスも持ってると思うんですよ。小さいものや目に見えないものの気配を感じて、そこに意味を見出す感覚って、日本っぽいな…と」
──各収録曲に、そういうマインドが反映されている。
「そうですね。生々しいグルーヴを追求したかったので、なるべく音を詰め込みすぎず、一音一音の微妙なニュアンスを大事にしたいなと思って。例えばフェンダーローズを弾くと、打鍵して指を離す時に軋む音がするんですけど、それがシンセでは表せない独特のグルーヴに繋がっていくんです」
──なるほど。あと、サード・シングルの「Stars In Your Eyes」は今作の中でもっとも歌モノ感の強いポップな曲です。以前「自分の歌はヴォーカルというより楽器の一部であるヴォイス」と仰っていましたが、歌に対する考え方は以前と変わりましたか?
「変わってきていますね。昔はそれこそ(声を)サウンドの一部として捉えていて歌の比重も少なかったのですが、最近は歌詞を書くようになって歌が増えてきているので。ただ、いわゆるシンガー/ソングライターと自分が違うなと思うのは、僕の場合はピアノとかいろんな楽器をやるし、トータルで表現したいものがあるので、歌だけで言い切らない。歌は未完成でもいいというか、隙間を残して、楽器を含めた全体で表現できればいいと思っているんです」

──かと思えば、セカンド・シングルの「Sit At The Piano」はピアニストとしての側面をストレートに伝えるインストですよね。
「今回は歌モノが多くて、制作を進めていくうちにもうちょっとインストも入れたいなと思って。それでピアニストとしての自分をフィーチャーした曲を作ろうと思ったんです」
──そういう意味では『pf_soul_01-08』(限定盤付属の作品集)も完全にピアニストとしての作品集。
「ピアノで表現したときに活きてくる曲を選びました。タイトルは “ピアノ・ソウル” と読むんですが、録ったままの生々しい感じを伝えたくて、レコーディング・データのファイル名みたいなタイトル(表記)にしたんです」
──カヴァーしているマーヴィン・ゲイの「What’s Going On」は以前リミックスもされていましたよね。
「ライブでもよく演奏していて、人生で初めてライブをやったときに演奏した曲でもあるんです(…とマーヴィンに関する熱い語りが続く)」
──ここまでの話を総合すると、今回の作品は、ご自身の快感原則に従った趣味性の強いアルバム?
「まず “自分が聴きたい音楽を作りたい” というのは大前提としてありました。僕は夜中にひとりで音楽を聴くのが好きなんですが、自分の音楽も大勢で聴いてワイワイ騒ぐようなものではなく一対一のものだから、夜中にヘッドフォンをつけて聴いたときにしっくりくるパーソナルな作品にしたくて。そうやって自分の気持ちに素直に作れば、同じ感覚の人たちに届く音楽になると信じてるんですよね」
Ghost Notes Tour 2019 開催決定!
詳細はこちら