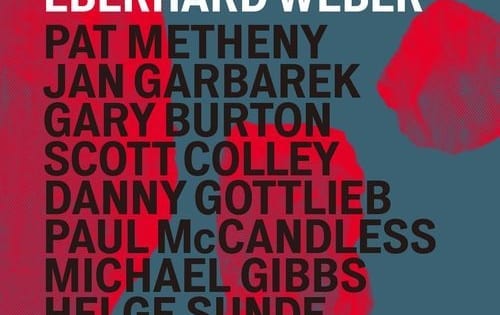投稿日 : 2017.05.29 更新日 : 2019.02.26
【ゲイリー・バートン】栄光のキャリアを静かに追想 そして、現役最後のステージへ 前編
取材・文/富澤えいち

——その結果、1968年にあなたは『ダウン・ビート』誌のジャズ・マン・オブ・ザ・イヤーを最年少で受賞しました。どんな気分でした?
「ジャズ・マン・オブ・ザ・イヤーの受賞は、記録に残る明確な評価だったので、正直言って、とても嬉しかったですね(笑)」
——その3年後(1971年)、モントルー・ジャズ・フェスティバルでのソロ・ステージのオファーを受けましたね。これは結果的に、あなたに最初のグラミー賞をもたらすことになった重要なステージです。
「『アローン・アット・ラスト』と題してリリースされたモントルー・ジャズ・フェスティバルでのソロ・ステージは、その名のとおり、私にとって最後のソロ・パフォーマンスにするつもりでした。まさに“実験”をするためにモントルーへ乗り込んでいったのです。そのステージでやろうとしていたコンセプションが聴き手に受け入れられるのかどうかは、まったく未知数のまま。そして確証がないまま、ライブ・レコーディングが行なわれたのです。レコーディングが終わった時点で、やろうとしたことができていたという感触はあったのですが、実際にモントルー・ジャズ・フェスティバルのコンサート・ホールにいた観衆のリアクションを見たときに初めて、それが成功したんだという実感が湧いてきました」
ふたたび母校へ……
バークリー帰参の真相
——1971年にはもうひとつの重要な出来事がありました。かつて学んだバークリー音楽大学に教員として舞い戻りましたね。
「1960年代の後半、私は多くのワークショップを行なっていました。同時に、ジャズを教えているときの自分がとても自然体でいられることに気づいたのです。そんな頃、アメリカ中西部の大学から、教師として招聘したいという提案がありました。しかし、場所がイリノイ州だったこともあって、各地をライブで飛び回るミュージシャン生活をしながら教鞭を執るのは難しいだろうと思って、引き受けられませんでした。でも、それがニューヨークからも近いボストンだったら可能なことに気づいて、ボストンにあるバークリー音楽大学なら自分の母校だし、教授陣やスタッフにも知人たちがまだ在籍していたので、逆にこちらから『ぜひ教鞭を執らせてくれないか』と掛け合ってみた、というのが真相なんですよ」
──その後、バークリー音楽大学の学長(Executive Vice President、1996~2003年)まで引き受けるわけですが、教員として教えるだけでは足りないものがあったということですか?
「私は1971年に教鞭を執るようになってから、退職する2003年まで、バークリー音楽大学に約30年間ほど関わっていたわけですが、教員として活動をするうちにレッスンだけではもの足りなくなり、より多くの生徒のために何かもっと大きな役割を果たしたいという想いが強くなっていきました。その想いが、私を学部長にして、最終的には学長へ導くことになりました。結果的に、この長年のバークリーとの関係が、大学の未来を築くための多くの選択肢を私に与えてくれたように思います」