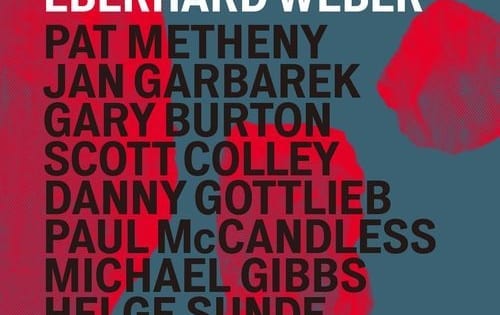投稿日 : 2017.05.30 更新日 : 2019.02.26
【ゲイリー・バートン】栄光のキャリアを静かに追想 そして、現役最後のステージへ 後編
取材・文/富澤えいち

ヴィブラフォンの奏法みならず、近代ジャズを刷新し続けてきたリヴィング・レジェンド、ゲイリー・バートンのインタビュー。
引退を前に、これまでのキャリアを振り返ったインタビュー前編に引き続き、後編は“最後の日本ツアー”のテーマでもある「デュオ」という、彼の代名詞的フォーマットに対する持論。そして、引退の花道を飾る“デュオの相方”小曽根真との交流について。
最初は乗り気じゃなかった?
デュオ・プロジェクト裏話
——それまでほとんど誰も手を付けていなかったデュオというフォーマットにあなたが注目したのはなぜだったのですか?
「きっかけはドイツのフェスティバルでした。『クリスタル・サイレンス』(1972年11月収録)を制作する少し前に出演したフェスで、主催側と『なにをしようか?』と話し合っているうちに、話の流れで『チック・コリアと2人だけで演奏するのはどうだろう』というアイデアが持ち上がったのです。やってみるとオーディエンスにとても好評で、チックが当時所属していたレコード会社(ECM)の関係者から『デュオとして作品を残すべきだ』と提案されたのです。じつは、私自身はデュオというフォーマットにぜんぜん乗り気じゃなくて、そのプログラムも成功するのか半信半疑だったんですよ(笑)。ましてやアルバムとして残すなんて考えられなかったので気が進まなかったのですが、周囲に説得され、ジャズ・フェスの2~3か月後にレコーディングが決まったんです。まさかその作品も評価されるなんて思ってもいませんでしたが、発売するとすぐに話題となって、ジャズ界でもデュオが珍しくないフォーマットのひとつになり、チック・コリアと私は現在に至るまでたびたびデュオでプレイすることになった、というわけです」
——『クリスタル・サイレンス』の収録にあたっては、どんなアプローチをしようと考えていたのですか?
「じつは、チックの曲を演奏するという以外、ほとんど何も決めていなかった。だから、まさに“偶然の産物”ですね。ただ、あの日のスタジオでは、2人それぞれのプレイというピースが“在るべき場所”にスッと収まって、カタチになっていく感覚を味わうことができました。その後も彼とデュオをするたびに新たな“化学反応”を起こし続けて、私にあのときと同じような感覚を味わわせてくれます」
.jpg)
——その後、ベースのスティーヴ・スワロウや、ギターのラルフ・タウナーとのデュオにチャレンジしたり、さらにチック・コリアとは何度もデュオを繰り返すことになります。デュオを続けようと思った理由と、繰り返すことができた理由を教えてください。
「デュオという演奏形態は、ほかのフォーマットでは味わえない喜びを私にもたらしてくれます。2人という最少人数の組み合わせは、より直接的な音楽的コミュニケーションをとることができるのです。人数が多いセッションでは、そこから生まれる音楽的な経験をプレイヤーの頭数で割らなければならないわけですが、デュオなら最大値でシェアができますからね。まさに、無二の親友と一対一で会話しているような感覚が相互に影響を及ぼし、さらに音楽的な可能性を広げてくれるのです」