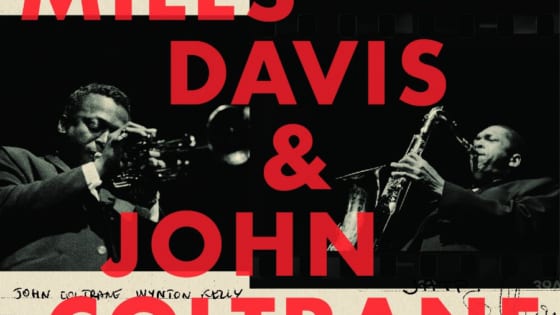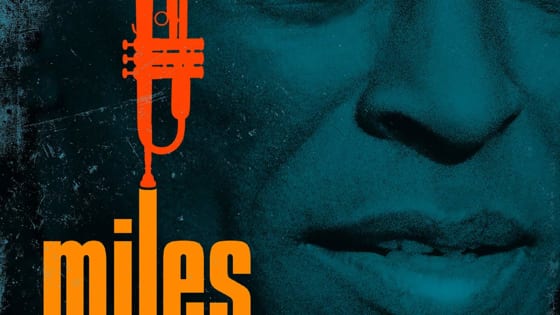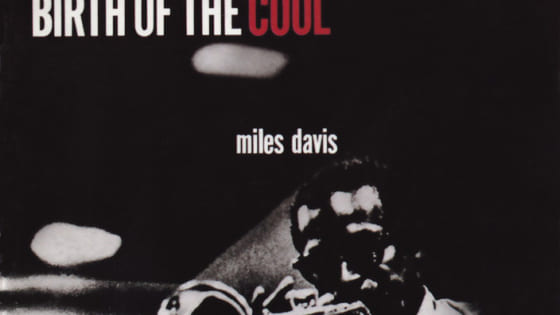投稿日 : 2019.08.15 更新日 : 2021.08.31
【マイルス・デイビス】なぜ人気? おすすめアルバムは? 知っておきたい5つのポイント
文/大門 炭

MENU
史上もっとも有名なジャズ・トランペッターのひとりとして知られるマイルス・デイビス。ジャズの歴史上、彼はどんな偉業を成し遂げたのか。そして、マイルス・デイビスとはどんな人だったのか。
生い立ちとキャリア
裕福な家庭に生まれて
マイルス・デイビスは1926年、アメリカ合衆国イリノイ州生まれ。歯科医の父親と音楽教師の母親のもと、当時のアフリカ系アメリカ人としては裕福な家庭で少年時代を過ごします。小学生でトランペットの演奏を開始した彼は、すぐに才能を開花させます。
最初のチャンスが到来したのは18歳のとき(1944年)でした。当時の人気バンド「ビリー・エクスタイン楽団」がマイルスの地元を訪れた際、トランペット奏者の一人が病気で休場。その代役として急遽、マイルスが参加することになったのです。
この楽団で彼は、当時のスーパースターとして知られていたアルト・サックス奏者、チャーリー・パーカーやトランペット奏者のディジー・ガレスピーらと初めて共演。マイルスはその感動が忘れられず、彼らを追ってニューヨークへ移り住みます。

ニューヨークに進出したマイルスは、憧れていたチャーリー・パーカーのバンドに加入(1945年)。徐々に頭角をあらわすと、メジャー・レーベル(コロムビア)と契約を交わし、あふれるアイディアを実現するために多くのバンドを結成。ライブやレコーディングを精力的におこないました。
バンドメンバーの変遷
第一期クインテット
1955年、マイルスは当時の名プレイヤーたちを誘って自身のバンドを結成します。5人編成のこのグループは、のちに「第一期クインテット」(注1)と呼ばれ、マイルスの初期のキャリアを語る上で重要なアルバム『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』(1956年)などを残しています。
注1:メンバーは、ジョン・コルトレーン(ts)、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)

この「第一期クインテット」を結成した3年後、彼はアルトサックスのキャノンボール・アダレイをメンバーに迎えて、セクステット(6人編成)に変更。自分よりも若いプレイヤーの情熱やアイディア、柔軟性に着目し、積極的に若手を採用しながら、新しいジャズのスタイルを模索し続けます。
第二期クインテット
なかでも有名なのが、1964年に結成されたグループ。「第二期クインテット」と呼ばれるこのバンドには、高い潜在能力を持った若手プレイヤーたち(注2)を起用。のちに彼らはジャズ界で大きな影響力を持つミュージシャンに成長します。
注2:ウェイン・ショーター(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)
そうした若手の能力を見抜き、伸ばす力は、のちのマイルス作品でも続きます。1960年代後半から70年代前半にかけては、ピアニストのチック・コリアやキース・ジャレットらを起用(注3)。80年代に入ると、ベーシストのマーカス・ミラーや、ギタリストのマイク・スターンらが抜擢され、メンバーそれぞれ、やがて名のあるミュージシャンとして活躍していきます。
注3:ほか、ジョン・マクラフリン(g)、ジョー・ザビヌル(kb)、デイヴ・ホランド(b)、ジャック・ディジョネット(ds)、アイアート・モレイラ(perc)なども、自身のバンドメンバーに抜擢。
変容を続ける演奏スタイル
ジャズ、と一口に言ってもさまざまなスタイルがあります。1940〜50年代にかけて流行した「ビバップ」というスタイルは、要約すると「指定されたコード(和音)進行に沿って、独自のメロディを演奏する」というルールの音楽でした。そしてミュージシャンたちは、そのルールの中でできるだけ速く、多くの音符を演奏することで自らの音楽を表現していました。
しかしゆったりと美しいメロディを表現したいマイルスにとって、ビバップは適したスタイルではありませんでした。自分に適したスタイルを模索するマイルスは、ビバップの命とも言えるコード進行を捨てることを決意。スケールと呼ばれる一定の音階(例えばドレミファソラシド)を使って自由にメロディ・ラインを奏でる「モード・ジャズ」というスタイルを生み出しました。
モードから生まれた最大のヒット作

このモード・ジャズのスタイルで作られた最初のアルバムは『カインド・オブ・ブルー』と名づけられ、1959年に発売。これまでに累計で1000万枚以上を売り上げる、ジャズ界最大のヒット作となりました。またこの作品は「モード・ジャズの完成形」とまで言われ、この作品を境に多くのミュージシャンがモード・ジャズを演奏するようになったのです。
ご法度のエレクトリック楽器を導入
1960年代後半に入るとマイルスはジェイムズ・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーン、ジミ・ヘンドリックスといった、ロック、ファンク、R&Bに関心を持つようになります。
その影響から、自分のバンドにもエレクトリック・ギター/ピアノ/ベースを取り入れるようになります。自身のトランペットにもワウ・ペダル(音色を加工する装置)を取り付けるなどして、ロックバンドさながらの音楽を作るようになりました。
こうして、“世紀の問題作“と呼ばれる『ビッチェズ・ブリュー』を1970年に発表。さらに、ファンク色を濃厚に取り入れた『オン・ザ・コーナー』を1972年に発表します。
ジャズ界のトップランナーとして、ビバップ〜モードへとシーンを導いてきたマイルスが、いきなりロックだ、ファンクだと言い始めたので、世のジャズファンやジャズ・ミュージシャンまでが「これはジャズだ!」「ジャズじゃない!」と喧々囂々、意見を二分して論争が巻き起こりました。

1980年以降になると、マイルスはポップスに急接近していきます。ポップ・ミュージック界で人気を博すマイケル・ジャクソンやシンディ・ローパーの楽曲を取りあげ、プリンスと交流を持つなど、ジャズを超えたポップスターになるべく奮闘。最晩年となる1991年には、当時世に広まりつつあったヒップホップの要素を取り入れ『ドゥー・バップ』を発表。同年の9月、マイルスは65歳で亡くなり、この作品が彼の遺作となりました。
マイルスと日本
マイルスは1964年の第二期クインテットの頃に(一部メンバーは異なるものの)初来日し、そのライブの様子は『マイルス・イン・トーキョー』というライブ・アルバムとなって残されています。初めて訪れた極東の地にもかかわらず、どの会場も満員で、毎回熱烈に歓迎してくれる日本のジャズ・ファンにとても驚いたということです。

それからというもの、スタイルを変えて何度も来日をしています。その中でも1975年に大阪でおこなわれたライブは、昼公演の『アガルタ』、夜公演の『パンゲア』という2対のライブ・アルバムとして残され、当時の熱狂を今に伝えています。
ライブ以外でのマイルスと日本の関わりで忘れてはならないのが、晩年のマイルスに対するタモリによるインタビューでしょう。
これは当時(1985年)放送されていた「今夜は最高」というテレビ番組の中での一企画。自らもジャズ・トランぺッターで、マイルスに憧れていたというタモリは始終緊張しています。それでもマイルスへのプレゼントに食品サンプルを渡すあたり、さすがは日本を代表するコメディアンというところ。一方マイルスは、インタビュー中に絵を描いてタモリにプレゼントしています。
現代に息づくマイルスのDNA
マイルスのバンドで育った若手ミュージシャンたちは、リーダーの強烈な音楽性に刺激を受け、バンドを卒業すると次々に自分のバンドを立ち上げ、ヒットを飛ばすようになります。
一部例を挙げると、ウェイン・ショーターとジョー・ザヴィヌルによる「ウェザー・リポート」、ハービー・ハンコックの「ヘッド・ハンターズ」、チック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエバー」、キース・ジャレットとジャック・ディジョネットの「スタンダーズ・トリオ」、ジョン・マクラフリンの「マハヴィシュヌ・オーケストラ」など、枚挙に暇がありません。
マイルスの死後も、彼か開拓したスタイルは現代に引き継がれています。特にマイルスが最後に残した「ヒップホップとの融合」は、ロバート・グラスパー(p)を中心とする若いミュージシャンが受け継ぎ、マイルスとは異なる手法で現在に花開かせています。

ここまででわかるように、マイルスは現状に留まることなく常に変化を続けてきました。ビバップと呼ばれるジャズの標準的な演奏方法を脱し、より自由にアドリブを取ることのできる「モード・ジャズ」を完成させた功績は、ジャズのみならず周辺の音楽へも大きなインパクトを与えました。音楽のルールを打ち破る型破りな活動を貫き、生前・死後を問わず各方面に大きな影響を及ぼしていたことから、マイルスは今もなお「ジャズの帝王」と呼ばれているのです。
【関連記事】