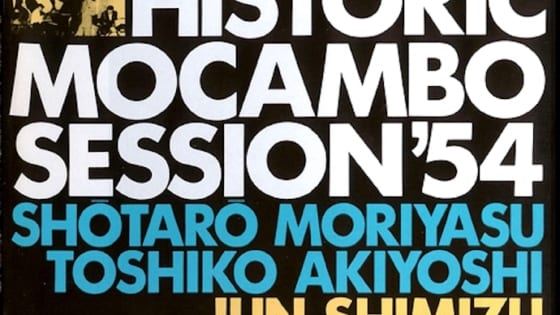投稿日 : 2020.12.01 更新日 : 2021.09.07
「テレビ芸能」の道なき道を切り拓いたクレイジーキャッツ【ヒップの誕生 ─ジャズ・横浜・1948─】Vol.19
文/二階堂尚

MENU
1960年代から始まる戦後日本の大衆社会は、多くの部分テレビによって形成されたものだった。日本人がテレビに熱狂した時代の最大のスター・グループの一つが〈クレージーキャッツ〉である。彼らはまた、戦後日本のジャズ・シーンから生まれた最大のスターでもあった。彼らはなぜスターとなることができたのか。あるいはこう問うてもいい。彼らは何と引き換えにスターとなったのか、と。戦後ジャズ・シーンにおける〈クレージーキャッツ〉の「生きざま」を検証する。
ジャズしかやらないバンドはクビ
「秋吉さんはジャズしかやらないのでよくクラブを首になった。仕事があまりなく、あっちこっちで演奏したが、結局仕事がなくなり、解散したり、また一緒に演奏したりの繰り返しだった」
秋吉敏子のリーダー・バンド〈コージーカルテット〉でアルト・サックスを吹いていた渡辺貞夫の証言である(『渡辺貞夫 ぼく自身のためのジャズ』)。ジャズ・ミュージシャンが「ジャズしかやらない」のは当たり前だろう、というのは現代の感覚で、当時まだジャズは人々が尊敬をもって鑑賞するアートではなく、店が酔客をもてなすBGMであり、ダンスの伴奏音楽だった。それはハワイアンやタンゴやカントリー、ときには日本の歌謡曲とも代替可能な音楽であり、多くのバンドは客の求めに応じてジャズではない曲を演奏した。しかし秋吉と、そのバンドを引き継いだ渡辺は違った。
「秋吉さんが渡米して、自分でバンドをもった時は、みんなに給料を払うと、月に千五百円くらいしか残らなかった。バンド・リーダーのつらいところだが、それでもポピュラーはやらないで、ジャズだけをやっていた。それでよくクラブを首になった。流行歌は絶対やらないし、お客がリクエストしても演奏しないから、首になるのが当然だった」(前掲書)
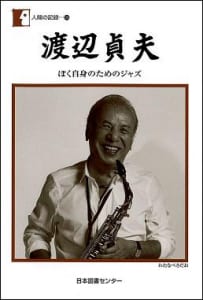
ジャズ・バンドからコミック・バンドへ
では、〈コージーカルテット〉と同時代に活動していた〈クレージーキャッツ〉はどうだったか。その活躍をリアルタイムでつぶさに見ていたエッセイストの小林信彦は、「クレージー・キャッツは、敗戦後のバンド・ブーム、のちのジャズ・ブームが生んだ鬼っ子である」と言っている(『日本の喜劇人』)。戦後のジャズ・シーンの中から生まれながら、結果としてジャズとは異なる場所で成功を収めたバンドだったからだ。
彼らが演奏に喜劇的要素を加えていったのは、もともと進駐軍クラブの米軍兵士を喜ばせるためだった。その方面に才能があったのは、リーダーでドラマーのハナ肇とトロンボーンの谷啓である。ハナの喜劇性はもって生まれたキャラクターの面白さに由来するものだったが、谷は子どもの頃からジャズと同じくらいアボットとコステロのヴォードビル(※1)や、マルクス兄弟(※2)が出演するコメディ映画を愛好していて、喜劇の勘どころをよく知っていた。〈クレージーキャッツ〉に入る以前、ビッグ・バンドでトロンボーンのスライド管を足で操作する谷の姿が目撃されている。「なぜ足を使うんだい?」と聞かれた谷は「だって、つまんないんだもん」と答えたという。彼一流のジョークだったに違いない。小林信彦は、〈クレージーキャッツ〉のクレージーたる部分の多くは、谷啓の一種の幼児的感覚に発していると言っている。
その二人以外にコメディの素養がもともとあったメンバーはいなかった。サックスの安田伸は東京藝術大学の管楽器科を卒業したエリートであり、植木等はビング・クロスビーやトニー・ベネットのようなクルーナー・スタイルのボーカリスト(※3)になりたがっていた。ベースの犬塚弘もピアノの石橋エータローも、当初はコメディをやることに大いに戸惑っていたようだ。石橋が結核で倒れたときに〈クレージーキャッツ〉に加入し、石橋復帰後もメンバーとしてバンドに残った「7人目のクレージー」桜井センリは、ロンドン生まれで小学生の頃からピアノを習い、秋吉敏子の後釜でビッグ・バンド〈ゲイスターズ〉のピアニストとなった才人だった。犬塚は、「桜井さんにコントをやらせるのが申しわけなくて仕方がなかった」と後年振り返っている。
初期のメンバーであった稲垣次郎もコメディをやることが嫌でバンドを離れている。「僕は、どっちかというとまともなジャズやブルースをやりたかったから、そのバンドからも離れていったわけ」と彼は語っている(『植木等伝』)。稲垣はのちに日本のジャズ・シーンを代表するサックス・プレーヤーとして知られることになる。

※1 バッド・アボットとルウ・コステロからなるアメリカのコメディアン・コンビ。1940年代から50年代にかけて映画やテレビで活躍した。ヴォードビルは笑いの要素を入れた軽演劇。※2 1910年代から40年代に活躍したアメリカのコメディ俳優のグループ。5人のメンバーは実際の兄弟だった。※3 抑制のきいた声でソフトに歌うスタイルのボーカルのこと。クロスビー、ベネットのほか、フランク・シナトラやナット・キング・コールなどがクルーナー・スタイルの代表的シンガーとして知られる。
テレビ時代とともに始まった快進撃
この頃の〈クレージーキャッツ〉の定番のネタの一つが「枯葉」(※4)だった。植木がクルーナー・ボイスで「枯葉」を歌い始める。1番が終わって間奏になるとハナ肇が葉の枚数を2枚、4枚、8枚と数え始める。枚数はそのまま倍々で増えていき。3桁の半ばになった頃に植木が「もう、おしまい」と口上を中断させ、何ごともなかったかのように2番を歌い始める。「おしまい」が枯葉を数える「枚」に掛かっていることは言うまでもない。こうして文章で説明してしまっては台無しであるという以上に、現代の感覚ではとくに面白いとも思えないギャグだが、小林信彦は「まったく類のない笑いだと、私はたちまち、とりこになった」という。演奏力のあるジャズ・バンドがこのようなギャグをステージでやるということ自体が当時は新しかったのだろう。
※4 第二次世界大戦直後に生まれたシャンソンであり世界的にヒットした楽曲。ジャズ界でも数多くのプレイヤーが演奏しレコーディングも多数。
これは言葉の芸だが、進駐軍クラブでのステージでは日本語は通じない。畢竟、身振り手振りを駆使した滑稽なアクションで笑いをとりにいくことになる。その様子を見た米兵が笑い転げながら「クレージー!」と叫んだことが〈クレージーキャッツ〉のバンド名の由来である。余談だが、この「動きで笑わせる」芸は、渡辺プロの後輩バンドである〈ドリフターズ〉にのちに引き継がれることになる。その代表的なものが、洗面器で頭を叩くギャグだ。ドリフはそれを天井から落ちる金だらいに転換して自分たちの定番ギャグとした。ドリフのメンバーの芸名はハナ肇が考えたものであり、国民的番組となった『8時だよ!全員集合!』のタイトルはハナ肇の口癖「全員集合!」からとられている。ドリフがクレージーから得たものは大きかったのである。
さて、〈クレージーキャッツ〉の快進撃が始まるのは、本格的なテレビの時代に入ってからである。NHK、日本テレビ、ラジオ東京(現TBS)に続いてフジテレビがテレビ番組放送を開始したのは1959年3月。その放送開始の翌日にスタートしたのが、〈クレージーキャッツ〉初のレギュラー番組『おとなの漫画』だった。毎週月曜から土曜の12時50分から始まる5分間の生放送で、時事ネタをテーマにしたコント番組である。この番組によって、〈クレージーキャッツ〉は全国区の人気芸能人となったのと同時に、本格的なコメディ・グループとなった。ジャズ界と芸能界を分かったあのモカンボ・セッションからわずか5年後のことである。
その後、ザ・ピーナッツとともにレギュラーを務めた日本テレビの『シャボン玉ホリデー』と、62年の東宝映画『ニッポン無責任時代』を皮切りとする映画出演によって、〈クレージーキャッツ〉は不動の国民的スターとなっていく。62年からの10年間で製作された「クレージー映画」は実に30本に及んだ。
テレビ視聴者という新しいオーディエンス
こうして〈クレージーキャッツ〉の歩みをたどると、彼らは進駐軍クラブやキャバレーの観客との妥協と引き換えに成功を手にしたように見える。秋吉敏子や渡辺貞夫や稲垣次郎は、オーディエンスに媚びることなく困難な狭い道を行った。いわばアートに誇り高く殉じる道を選んだ。しかし〈クレージーキャッツ〉は、稲垣が言う「まともなジャズ」をいわば裏切ることによって、芸能人となりスターとなった──。
この見方が的を射ていると言えないのは、彼らが選んだエンターテイメントの道もまた狭い道にほかならなかったからである。彼らが決してオーディエンスに媚びを売っていたわけではないことを示すこんな発言がある。
「僕らはね、いよいよとなったら楽器の演奏すりゃいいや、ってな気持ちだったからね。だから、必要なこと以外はあまりバタバタしない、必要なこと以外余計なことは喋らないみたいなね、ある意味愛想なしのところがあったの。分からなけりゃ分からなくていいや、みたいなね。無理にウケようとか、客に媚びるとか、そういうことは殆どなかったね。ずーっとマイペースでやってたから」(『植木等伝』)
バンドのイメージを覆すようなこの発言を晩年の植木等から引き出したルポライターの戸井十月は、こう書いている。
「『クレージーキャッツ』のギャグは、どれだけベタなことをやってもハチャメチャやっても、どこか垢ぬけていてクールでスマートだった。……『クレージーキャッツ』は、ステージの上でドタバタするコミックバンドであるより以前に、シャイでニヒルな実力派ミュージシャンたちの集まりだったのである」

その実力を半ば封印し、バラエティ番組の定型が一切ない時代に、テレビ視聴者という新しいオーディエンスを楽しませるという道なき道を彼らは行った。秋吉敏子や渡辺貞夫が「日本人によるモダン・ジャズ」という道なき道を行ったように。それぞれの選択は、自分たちが何をやりたいか、何を自分の生きがいとするか、何を人々に与えたいかと考えた結果であるという点で等価だった。選んだ生きざまが異なっただけである。
日本が高度成長時代に入ろうとしていた1950年代の半ば、戦後のジャズ・シーンでしのぎを削っていたミュージシャンたちはそれぞれの道を歩み始めた。その足跡が、一方では戦後日本のジャズ史として、一方では戦後日本の芸能史として確かに残されたのである。
(次回に続く)
〈参考文献〉『渡辺貞夫 ぼく自身のためのジャズ』渡辺貞夫(日本図書センター)、『ハナ肇とクレージーキャッツ物語』山下勝利(朝日新聞社)、『日本の喜劇人』小林信彦(新潮文庫)、『植木等伝「わかっちゃいるけど、やめられない!」』戸井十月(小学館文庫)、『最後のクレイジー 犬塚弘』犬塚弘/佐藤利明(講談社)
▶︎Vol.20:昭和を駆け抜けたヒップスター ─クレージーキャッツと高度成長時代
1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。