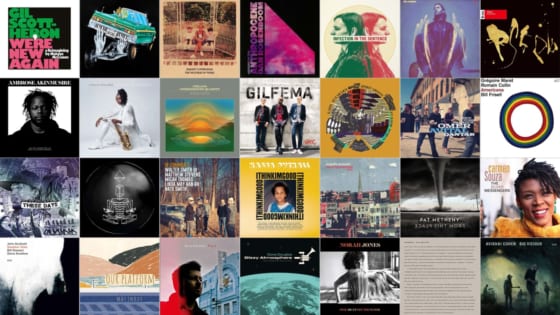投稿日 : 2021.06.28 更新日 : 2025.02.14
「これまでのジャズ」と「これからのジャズ」─村井康司 インタビュー

日本人のジャズ観
──とはいえ現在も、特に日本では “モダンジャズ至上主義”みたいな雰囲気が強い気がしますね。もちろん、それほどに多くの人の心を掴む魅力的なスタイルであるわけですが。
村井 確かに日本のジャズファンの多くは、いわゆるモダンジャズを好みますね。それ以前と以後をすっ飛ばして、まあ、チャーリー・パーカーからジョン・コルトレーンまでかな。その20年ほどの期間が「ジャズ」の対象。もちろん全部のジャズファンがそうだということではないですけど、そういう人がきわめて多いのは確かです。ただ、それって「かつてのジャズ観」に対する修正がはたらいた結果でもあるんですよね。
──というと?
村井 日本の場合、第二次世界大戦の前からジャズが入ってきていて、聴いている人もいたしジャズ評論家もいたわけです。野川香文(1904-1957)とかね。彼の書いたものを読むと、意外と白人のジャズが多いんですよね。
──最近、野川香文の著作『ジャズ音楽の鑑賞』が復刊されましたね。

村井 あれを読むと、ポール・ホワイトマンに対する記述がすごく多いですよね。面白いな、と思って。あの本が出たのが1948年ですから、戦争が終わって1950年くらいまではポール・ホワイトマン、グレン・ミラー、ベニー・グッドマンとか、そういうものをジャズの中心と捉えていたわけですよね。
これに対して「じつは違うんだよ」と言ったのが、油井正一さんや相倉久人さん。“黒人のやってるジャズ”が本物であって、ポール・ホワイトマンがジャズ王なんてのは嘘です、みたいなね。これはある意味、正しい認識ですけど、そこをあえて意識的に戦略的に、強く出したんだと思うんですよ。
──なるほど。まあ確かに、ロックだってエルビス・プレスリーやビートルズじゃなくて、ほんらい黒人のものだ。っていう言い方だってできますからね。
村井 当時は『スイングジャーナル』のような雑誌の力がすごく強かったから、そこで油井さんが記事を書き、あるいはレコード会社が作品を出すときに油井さんが監修者になって、チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーのような「黒人音楽としてのジャズ」を強く打ち出した。そこは意図的に強く押し出していた可能性はあると思う。
──そうした(60年代の)雑誌や書籍、レコードなどが「ジャズ=アフリカ系アメリカ人の音楽」というイメージを強くした。加えて、当時の日本のジャズファンにとって重要な拠点だったジャズ喫茶も、おおむね同じスタンスをとったわけですよね。
村井 そうすると「ビバップ以降の黒人のジャズが本物である」みたいな雰囲気が作られていく。もちろん、(ビバップ以前の)スイングやデキシーも根強いファンがいますが、だんだん減ってきて、いわゆるモダンジャズのファンが大きくなっていった。
さらにその頃、アート・ブレイキー&ザ・ジャズメッセンジャーズが来日(1961年)。あれはまさにファンキージャズですから “ブラックミュージックとしてのジャズ”を象徴するような存在ですよね。
──それを機に、ちょっとしたジャズブームが起きたそうですね。
村井 そうしたことも相まって “ブラックミュージックとしてのジャズ” がメインストリームになってゆくのだと思います。その後もフリージャズ的なものが出てくるわけですが、これもまさにアフリカン・アメリカンの音楽だった。その象徴がコルトレーンですよね。そうして70年代を迎えるわけですが、もう、それ以降のものは聞かなくていい、となるんですよね。
── “それ以降のもの”とはつまり、70年代に発現した「フュージョン」ですね。これは多くのジャズファンに軽視されてきた “ジャズの一形態”ですが、冒頭で話したとおり、現代のジャズを読み解く上でとても重要なファクターだと思うんです。
フュージョンを取り巻く状況
──村井さんは著書『あなたの聴き方を変えるジャズ史』の中で、“なぜ、あの時期にフュージョンが流行ったのか”を分析していて、マイルス一派のエレクトリック・ジャズや、イージーリスニング、ソウルジャズ、ブラスロックなど、いくつかの素因が絡み合ってブームが起きた、と説明しています。

村井 無理やり誰かがでっち上げたブームでは全然ない。長い年月の中でいろんなことが起きていたのが、ある時うまくくっついちゃって、という感じがすごくありますね。
『スイングジャーナル』の編集長だった中山康樹さんが、かつてこんな事を言ってました。「若い頃、ジャズ喫茶に行ってゲイリー・バートンとかリクエストするとすごく嫌な顔された」と。これは彼が10代の終わりくらいのときだから、60年代の終わりから70年代初めの話。当時の彼はロックと並行してジャズを聴いていたから、自分のセンスに合うジャズって、エレクトリックなマイルスや、ゲイリー・バートン、ラリー・コリエルとか、その辺だった。
ところが、彼より年上のジャズファンの間では、そういうものはすごく嫌がられていた、と言うんです。年上と言っても当時25〜30歳くらいだろうけど、その人たちは「ああいうのはニセモノだ」ってことを言っていた。そんな事を話していましたね。
──ちなみに村井さんご自身は、当時の空気をどう感じていました?
村井 僕がジャズを聴き始めたのは、その少し後。高校生のときだから73年くらいかな。ちょうど、リターン・トゥ・フォーエバーの最初の作品“カモメ”と呼ばれてたやつが出て、そのすぐ後にヘッドハンターズが出て、っていうタイミング。これを新譜で聴いた。それまではずっとロックを聴いてましたけどね。

──73年のチック・コリア(リターン・トゥ・フォーエバー)とハービー・ハンコック(ヘッドハンターズ)。高校生の村井さんにはどう聞こえました?
村井 素直に「これ、かっこいいじゃん」と思いましたよ。でもジャズ喫茶に行くと「そんなのはかけません」とか「うちにはありません」みたいな対応されたり(笑)、そういう店もあリました。
巨大台風だった「Breezin’」
──当時はフュージョンとかクロスオーバーという言葉で一括りにされていたようですけど、そのサウンドはかなり多様性がありますよね。
村井 うん、たとえばその頃、ジョン・マクラフリンのマハヴィシュヌ・オーケストラとかも出てきて。これはいわゆるフュージョンよりも、もう少しハードな感じでよすね。そういうものや、ウェザー・リポートはOK、みたいなジャズ喫茶も結構あって。当時の僕は「その違いは何なの!?」と思ったけど、しばらくして「あ、なるほどな…」と。ちょっとわかりにくくて、即興演奏の比率が高いとオーケーなんだなあ、とね。
でもやっぱり、ジャズファンの多くがいちばん好きだったのは、わかりやすいハードバップなんですよね。70年代のその頃になると、フリー・ジャズはあまり聴かれてなかったという記憶があります。
とはいえ、当時の(フュージョン路線の)チック・コリアやハービー・ハンコックを好きな人もいっぱいいたし、嫌がられつつも「まあ、これもジャズだ」と許容されていた感じはありましたね。
──完全に潮目が変わったな、と感じたのはいつ?
村井 『ブリージン』です。76年だから僕が大学に入った年ですけど、これに対しては「あれはジャズじゃない」と言う人はいっぱいいて、実際、それまでジャズなんか聴いていなかった人たちにも支持されてましたね。

──ジョージ・ベンソンの『ブリージン』。これを聴いた村井さんの反応は?
村井 かっこいいと思いましたよ。同じ年に「スタッフ」の最初のアルバムも出て、これもいいな、と。確かにあの辺の音を、明確なジャズだと言うのは難しいですけど……まさにクロスオーバーですよね。
この時代になるとロックもあるていど成熟してきて、ハード・ロックだけじゃなくて広い意味でロックを楽しむ人たちも結構いたんですよ。彼らはすでにスティーヴ・ガッドやコーネル・デュプリー、エリック・ゲイルとかの名前はよく知っていた。なぜなら自分が聴いているレコードで演奏しているから。

──凄腕のスタジオ・ミュージシャンとして。
村井 そう、どっちかというと裏方ですよね。そういう人たちがバンド組んでアルバムを出した。アメリカンロックやシンガー=ソングライター、初期のAOR的なものを聴いている人たちは、すでに「スタッフ」のメンバーの名前は知っていたし、クルセイダーズのラリー・カールトンやジョー・サンプルの存在も知っていた。そっちの方からお客さんがどっと流れてきた印象はありますね。
次ページ>>クインシーは知っていた