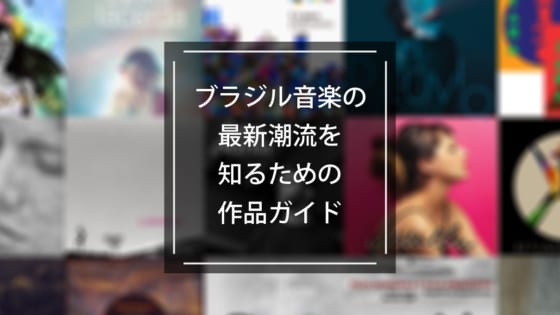投稿日 : 2021.10.22 更新日 : 2022.06.03
挾間美帆の新作と「ラージ・アンサンブルの歴史」を一気に解説 ─おすすめ作品リストも

ジャズ・ビッグバンド/ラージアンサンブルのおすすめ15作
選・文/村井康司
挟間美帆の『イマジナリー・ヴィジョンズ』に至るビッグバンドの流れ、という意図で選んだ15作品だ。ビッグバンドを「サウンド派」と「スウィング派」に分けるとしたら、ここで選んだバンドは、「スウィング派」代表選手のカウント・ベイシー以外は「サウンド派」だと言っていい。
クラシックとジャズの融合を1920年代に目指したポール・ホワイトマン楽団、特に作曲者のガーシュイン自身がピアノを弾いた「ラプソディ・イン・ブルー」も聴いてみてほしいし、ここでは敢えて採り上げなかった30年代のスウィング・バンド、ベニー・グッドマンやグレン・ミラーも機会があればぜひ。
なお、現在CDで入手しにくいタイトルもあるが、それらもストリーミングや配信で聴けるものを選んである。
『ザ・ポピュラー・デューク・エリントン』(RCA 1966)
デューク・エリントン・オーケストラ

エリントンは1920年代から70年代までの間に膨大な数の作品を遺したが、最初に聴くならこれをお薦め。ステレオのいい音で、エリントンの代表曲が楽しめるというだけでなく、よく聴くと「なんじゃこりゃ!」と驚愕する不思議なハーモニーや楽器の組み合わせが隠されているから油断できない。特に「ムード・インディゴ」「ソフィスティケイテッド・レディ」がとんでもない響きだ。
『ビリー・ストレイホーンに捧ぐ』(RCA 1967)
デューク・エリントン・オーケストラ

1939年から亡くなる67年まで、エリントンと一心同体となって活動した作編曲家、ビリー・ストレイホーンの楽曲を演奏した追悼作。二人の作曲と編曲は非常によく似ているのだが、「ブラッドカウント」「ロータス・ブロッサム」など、ストレイホーンの曲の方がメランコリックな色彩が強い。ここでも随所に謎のハーモニーが登場している。
『ベイシー・イン・ロンドン』(Verve 1956)
カウント・ベイシー・オーケストラ

ややこしいこと言わずにとにかくスウィング!というベイシー楽団の長所が全開になったライヴ盤。ソニー・ペインのドラムスを中心に速いテンポでぶっとばす「ブリー・ブロップ・ブルース」などの曲もいいけど、ミディアムの「シャイニー・ストッキングス」や「コーナー・ポケット」での、フレディ・グリーンのリズム・ギターにしびれます。
『Claude Thornhill and His Orchestra Play the Great Jazz Arangements of Gil Evans, Gerry Mulligan, and Ralph Aldrich』(Fresh Sound 1942~52)
クロード・ソーンヒル・オーケストラ
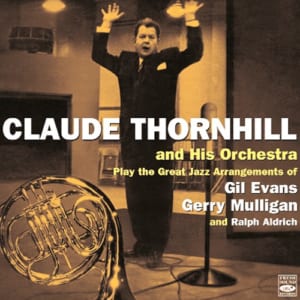
40〜50年代に活躍したソーンヒル楽団は、もともとはセンスのいいダンス・バンドだったが、ギル・エヴァンスがアレンジャーとなって先進的なサウンドを奏でるようになった。これはギル、ジェリー・マリガン、ラルフ・アルドリッチが編曲したレパートリーを集めたもので、マイルスの『クールの誕生』に直結するサウンドがたっぷり聴ける。
『スタン・ケントン・プレゼンツ』(Capitol 1950)
スタン・ケントン・オーケストラ

ケントン楽団はアート・ペッパーやジューン・クリスティなどの素晴らしいミュージシャンをずらりと揃えたビッグバンドだったが、このアルバムは45人編成(!)によるゴージャスかつアヴァンギャルドな異色作。メンバーの名前をタイトルに付けた曲と、ほとんど現代音楽としか思えない「ハウス・オブ・ストリングス」にのけぞってください。
『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(Solid State 1967)
サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラ

作編曲家でトランペッターのサドとドラマーのメルが、ニューヨークの一流どころを集めたビッグバンド。ハード・バップ的だけどハーモニーが先鋭的なサドの曲を、腕利きたちが伸び伸びと演奏し、各人のソロもさすがの出来栄え。「リトル・ピキシーⅡ」での、ブラスとサックスの延々と続く掛け合いアンサンブルに興奮しましょう。
『ニュー・ライフ』(Horizon/A&M 1975)
サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラ

初期からかなりメンバーが交替したが、70年代のサド=メルも実にクオリティの高いビッグバンドだった。フレンチ・ホルンやチューバを加えた曲、サックス・セクションが木管楽器に持ち替えて美しいアンサンブルを聴かせる曲など、ヴァラエティに富んだ選曲がいい。メンバーのセシル・ブリッジウォーターの「ラヴ・アンド・ハーモニー」は名曲。
『サンダリング・ハード』(Fantasy 1974)
ウディ・ハーマン・オーケストラ

ハーマン楽団は40年代後半の「フォー・ブラザーズ」の頃も素晴らしいけど、新しいサウンドに挑戦していた70年代もお薦めしたい。ここではコルトレーンの「レイジー・バード」が特にいい出来で、トレーンのサックス・ソロを採譜して、フリューゲル・ホーン+サックス・セクションのアンサンブルで聴かせるのが実にかっこいい!
『プリースティス』(Antilles 1983)
ギル・エヴァンス・オーケストラ
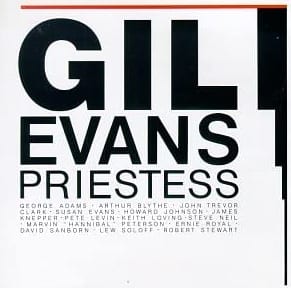
ギル・エヴァンスは70年代に入ってエレクトリック・サウンドを採り入れるようになったが、77年のこのライヴが個人的にはいちばん好きだ。タイトル曲でのデヴィッド・サンボーンとアーサー・ブライスのアルト・ソロ・バトル、気合いが入りまくっているルー・ソロフのトランペット・ソロ、寄せては返す波のようなホーン・アンサンブルが快感です。
『Mel Lewis & the Jazz Orchestra Play the Compositions of Herbie Hancock Live in Montreux』(MPS 1980)
メル・ルイス・オーケストラ

サド・ジョーンズと別れてからのメル・ルイスはさまざまな作編曲家と仕事をしたが、このハンコック曲集のアレンジャーはサックス奏者でもあるボブ・ミンツァー。モダンで重層的なハーモニーを持つハンコックの曲を、ミンツァーはごく自然にビッグバンド・アンサンブルとして落とし込んでいる。80年代の学生ビッグバンドの憧れの的、でした。
『Bob Brookmeyer – Composer/Arranger』(Gryphon 1980)
メル・ルイス・オーケストラ

このアルバムでメルが楽曲を依頼したのは、50年代からの付き合いでサド=メル楽団にも参加していたボブ・ブルックマイヤー。モダニズム建築のように精緻に構成された「スカイラーク」から、クラーク・テリーのトランペットをフィーチュアして楽しく盛り上がる曲までヴァラエティに富んだ仕上がりで、ブルックマイヤーの手腕が光っている。
『ミュージック・フォー・ラージ・アンド・スモール・アンサンブル』(ECM 1990)
ケニー・ウィーラー

ウィーラーはカナダ出身でイギリスで活動していたトランペッター。ラージ・アンサンブルの作編曲家としても超一流で、ここでは50分近くの大作や、サンバのリズムだけど実にクールでスタイリッシュな「ソフィー」など、他の誰とも違う個性的な曲作りを全開にしている。メンバーはイギリス・ジャズ界の大物とアメリカの名手の混成チーム。
『Centennial』(artistShare 2012)
ライアン・トゥルースデル

1988年に亡くなったギル・エヴァンスが遺したスケッチを元に、作編曲家のトゥルースデルが「もしかしたらこうだったかもしれないギルの曲」を構築し、大編成バンドで録音した作品で、ギル生誕100周年の2012年に発表された。半音がぶつかったり不思議な楽器の組み合わせが随所に出てくるギルは、やはりエリントンから大きな影響を受けていたのだろう。
『Real Enemies』(New Amsterdam 2016)
ダーシー・ジェームス・アーギューズ・シークレット・ソサエティ

ダーシー・ジェームス・アーギューもギル・エヴァンスやサド・ジョーンズの影響下にあるコンポーザーだが、ダークでパンキッシュでもある独自の世界観を持った存在だ。ここでの監視社会や「内なる敵」についてのシアトリカルな構成は、社会が分断され緊張感が増していくアメリカ社会の投影なのかもしれない。コロナ禍の今こそリアリティを感じる音楽。
『Data Lords』(artistShare 2020)
マリア・シュナイダー・オーケストラ

21世紀のラージ・アンサンブルをリードしてきたマリアの最新作は、共演したデヴィッド・ボウイからの影響を感じさせる暗い緊張感を湛えた楽曲が多く含まれている。それまでピースフルな曲が多かったマリアだが、2枚組の1枚目が「データ社会の暗黒面」を語るダークなサイドになっている。2枚目は従来の延長といえるゆったりとした曲が中心。