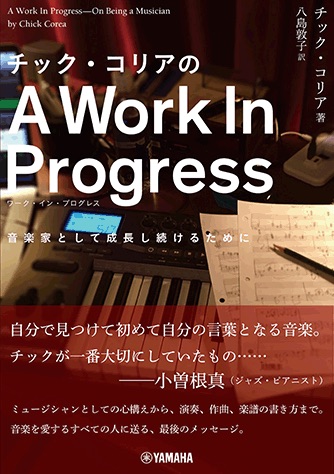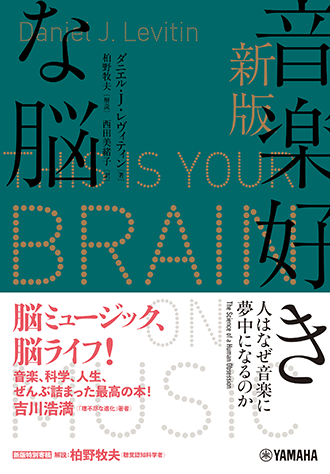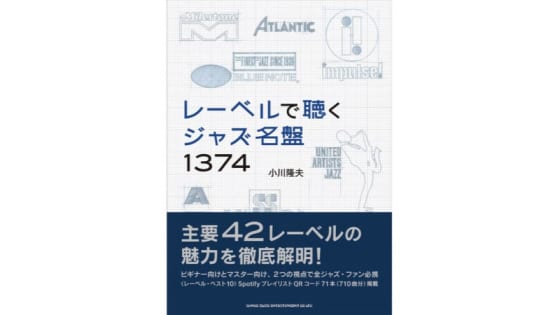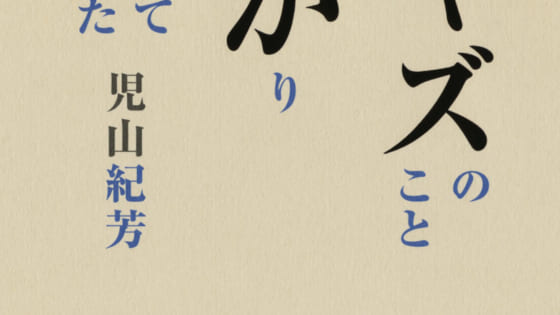投稿日 : 2022.02.28
この国は「音楽」をどう受容してきたのか─ 『ニッポンの音楽批評150年100冊』著者インタビュー
取材・文/二階堂 尚

近代以降の日本の音楽批評の歴史をわかりやすくまとめ、ブック・ガイドを付した『ニッポンの音楽批評150年 100冊』(立東舎)が話題になっている。著者は、文芸や経済のフィールドでも活躍する栗原裕一郎氏と、菊地成孔との共著シリーズで知られる大谷能生氏だ。今までありそうでなかった「音楽をめぐる言説」の通史。その執筆の裏側と、音楽本の可能性について、2人に語ってもらった。

冗談から始まった「音楽批評の批評」
──企画のきっかけは、10年くらい前のちょっとした雑談だったとまえがきに書かれています。
大谷 とある打ち上げの席で栗原さんと一緒になったときに、「最近、いい音楽批評の本が多いよね」という話が出て、それをテーマに企画がつくれないかなとか言って盛り上がったんです。もともとはほぼ内輪うけの冗談で、その年に出た音楽本に「渋谷陽一賞」とか「中村とうよう賞」を僕たちが勝手に進呈しちゃおう、みたいな話でした(笑)。で、とりあえず連続イベントをやろうという話になったわけです。

栗原 全部で5回くらいやりましたかね。最初はペリー来航から歴史に沿ってやっていったんだけど、だんだんテーマが細分化されていきました。小林秀雄特集とか。

大谷 最初にイメージしていたのは、栗原さんと書評家の豊崎由美さんの対談をベースにした石原慎太郎本(『石原慎太郎を読んでみた』原書房)でした。僕は以前から菊地成孔さんと講演やトーク・イベントをベースに共著をつくるということを何度もやってきましたから、このスタイルは得意なんですよ。
栗原 一緒に書いた村上春樹本(『村上春樹の100曲』立東舎)も、イメージとしてあったよね。
大谷 5人で書いたやつね。あれはディスク・ガイドでしたが、わりと評判がよくて、海外で翻訳が出たりしたんです。あの本にならってブック・ガイドをつけちゃおうということになって、一気に企画が固まりました。それが3年前くらいの話です。
──始まりは冗談でも、結果的にとても充実した内容で、かつリーダブルな本になっていますよね。音楽批評史というだけでなく、日本の洋楽受容の通史として成立しているように思います。
栗原 思うに、音楽批評史は「音楽をどう聴き、どう語ったか」ということの歴史なので、それはおおむね音楽の受容史になってしまうわけです。面白いのは、日本における近代の洋楽受容は、ほぼ文学者によってなされていたということです。実際の音を聴いたこともないのに音楽について語るというところからまず入っているという。
大谷 1900年代初頭のワーグナーに対する熱狂がその典型ですよね。まだきちんとした録音もないのに、文学者を始めとする知識人がみんなワーグナーについて語り出した。それは結局、ニーチェがワーグナーについて書いたからです。
栗原 音楽に関する文学者の紹介文や批評文を読んで、その音楽について想像し、熱中する。それもまた音楽受容の一つのあり方ということです。
──音楽をめぐる言葉が音楽以前にあったわけですね。それだけ、音楽に関する言説に力があったとも言えそうです。
大谷 そういう言説の力が急激に失われたのが2000年代に入ってからです。今はもう、テキストからアーティストや作品に関する知識を得て、その上で音楽に向かうという行動はほぼないでしょう。
栗原 雑誌が読まれなくなったことが大きいと思います。今は、Spotifyのプレイ・リストで音を聴いて、情報が知りたければ検索するといったスタイルが主流になっていますよね。
難しい話はやめてブック・ガイドに
──構成づくりや執筆に当たって、一番苦労したのはどこでしたか。
栗原 企画が固まる前に、「批評って何だろうね?」という話をよくしていたんですよ。音楽を語ることの欲望や、音楽に熱狂する衝動の根っこにあるのは何か、という話です。そこで最初に立ち止まって考え込んでしまいました。

大谷 批評を書くリビドーって音楽においては何だろう、という問いですよね。イベントではそういう原理論的な話もしていたのですが、それを本にしようとするとすごく分厚くなっちゃいますから、ごっそり削ったんです。難しい話はとりあえずやめて、ブック・ガイドを入れてエンタメの方に振っちゃえと。そこでようやく本の方向性が定まりました。
──批評は音楽をメタの視点で捉える行為であり、その歴史を記述することは、いわば「メタのメタ」の視点で語ることになりますよね。その難しさを感じたりはしませんでしたか。
大谷 僕は、音楽の流れと音楽批評の流れが2つあって、どちらが上とか下ということではないと考えています。音楽が言説を生み出す場合もあるし、言説が音楽を受容させる場合もあるわけで、その両方の流れを立体的に伝えられればいいと。
──なるほど。構成を見ると、幕末以降の歴史が30年単位で区切られていて、全5章で150年をカバーするつくりになっています。最後の5章だけがお2人の対談ですが、これはどういう狙いだったのですか。
大谷 最後の30年は2025年までで、未来が入っちゃっているんです。だから、力不足で書き切れなかったというのが本当のところです。あの章は「あとがき対談」くらいのイメージで読んでいただけたらいいと思っています。この本が文庫になった暁には、ぜひ書き起こしたいですけどね。
栗原 もう一つ、さっき大谷さんが言ったように、2000年代以降、批評の力が急速に衰えてきたという事情もあります。批評活動は最終的に広義の「広告」にハックされてしまった。音楽をめぐる言説はリコメンドか紹介文だけになってしまった──。それが僕たちの見立てです。その時代を記述するのはまだ難しいだろうという判断がありました。
──ブック・ガイドのページでは、各時代20冊、計100冊が選ばれています。読むという点でも選ぶという点でも、相当力量のいる作業だったと思いますが……。
大谷 2人で候補を挙げては削りという作業を繰り返して選んだのが、この100冊です。候補に挙がった数でいうと、この3倍くらいはあったと思います。とはいえ、ほぼ2人が読んできた本の中から選んでいるので、それほど選定に時間がかかっているわけではありません。
栗原 100冊のブック・ガイドを入れるというアイデアが出たのは、確か出版の1年くらい前でしたから、選定と書評執筆には1年もかかっていないですね。
──深沢七郎の『楢山節考』など意外な本もセレクトされています。選定の基準はあったのですか。
栗原 単純にお互いが読んできたものの中から面白いものを出し合って、あとは全体のバランスを見ながら、加えたり省いたりしていきました。
大谷 一つ基準があったとすれば、デビュー作を選ぶということですね。たくさんの著書がある人でも、最初の一冊を取り上げることにしました。そうしないときりがないですし、それによってその人が世に出たタイミングと時代の相関も見えてきますから。
良質な音楽本が増えている理由
──お2人とも共著というフォーマットでのお仕事が多いですよね。これまでの共著と今回の本とで、作業面などでの違いはありましたか。
大谷 共著のつくり方はケースバイケースですが、今回は全体のイメージや構成はほぼ僕が決めました。栗原さんが何もやってくれないから(笑)。

栗原 共著は、船頭が複数になると難しい場合が多いんですよ。それぞれがガチで意見を言い合うと、なかなかまとまらなくなってしまう。今回は大谷さんに船頭を任せることでうまくいきましたね。
──音楽をつくる際は共同作業が普通ですが、執筆は一人でやるケースが一般には多いと思います。共著というフォーマットのメリットをどう感じていますか。
大谷 音楽は共同作業の中で、お互いの一番いいところを融合させていくわけですよね。本をつくるときも僕はそのやり方が気に入っていて、『共著の達人』という本を出したいくらいです(笑)。自分で原稿を書いて、ほかの人の原稿が来るのを待って、それをまとめて、修正して、校正して、一つの作品に仕上げていくという過程が好きなんですよね。
栗原 僕は筆が遅いので、単著だとなかなか本が出来上がらないんです。『石原慎太郎を読んでみた』は約10年前の本ですが、単著だったらまだ出せずにいた可能性はけっこうありますね。慎太郎の訃報に間に合わなかったかもしれない(笑)。でも、共著の場合は他の人がいるのでどうしたって進めなければならず、作業にブーストがかかる。それが共著の一番のメリットですかね。
──書籍市場は1996年をピークにほぼ右肩下がりを続けています。一方で、音楽本の発刊点数はこの数年増えているような気がしますよね。
栗原 おそらく、雑誌の衰退と関連しているのではないでしょうか。以前の音楽ジャーナリズムの中心は雑誌でしたが、2000年代に入って雑誌媒体の数も部数も大きく落ちていって、書き手が書籍にシフトしていったということなのだと思います。
大谷 良質な研究書もたくさん出ていますよね。音楽の本を書く立場からすると、参照できる本が増えて非常にありがたいです。
栗原 ポピュラー音楽の研究者は以前より多くなっていますね。それが出版点数だけでなく、質の高さに結びついているのだと思います。
音楽を聴いているだけでは優れた音楽の本は書けない
──今後取り組んでみたい企画はありますか。
栗原 この本の続編でもう100冊紹介する本なら、すぐにでも書けるかな。
大谷 それは簡単にできるでしょう(笑)。僕が今興味があるのは、戦前、というかほぼ江戸時代で、今は1700年代くらいのことを調べています。都々逸とか語り芸のような邦楽を、既存の邦楽業界の外側から、大衆音楽として、今日的な視点で見ていくのが面白いなと思っています。
栗原 今回の本の流れで言うと、日本の音楽批評の流れをつくった評論であり、それゆえに呪縛にもなっている小林秀雄の「モオツァルト」を一度丁寧に解きほぐしてみたいですね。あとは先ほど話にも出た、19世紀末から20世紀初頭にかけて明治文壇に吹き荒れた病的なワーグナー・ブームの箇所への反応が多いので、このブームに端を発する文学者の音楽受容の系譜を辿ってみるのも面白いかもと考えているところです。
──最近の本で、今後の音楽批評の可能性を示す一冊がありましたら、最後にご紹介いただけますか。
大谷 伏見瞬くんの『スピッツ論』(イースト・プレス)は面白かったです。いわゆるジャーナリズム的な批評ではなく、文芸批評とか映画批評の方法論を取り入れた音楽論で、蓮見重彦さんなどの影響も感じます。

栗原 僕が本質的に新しいと思ったのは、ドナルド・フェイゲンの代表作である『ナイトフライ』を題材にした、冨田恵一さんの『ナイトフライ』(DU BOOKS)ですね。「ポピュラー音楽にとって、録音による記録こそが、音楽を彫琢するための記号である」というのがこの本の趣旨で、音楽の作り手側が専門的技術を開示することで読み手の音楽リテラシーを更新し、音楽の聴き方を変えてしまうという画期的な本です。

大谷 一つ思うのは、音楽を聴いているだけでは優れた音楽の本は書けないということです。さまざまな芸術ジャンルの関係性や人間の歴史に対する認識をもちながら、音楽を聴く耳があって、かつ一冊の書籍の世界を構築する力がある。そういう人からしか新しいものは生まれないと思います。そんな人がいろいろなジャンルから出てきて、これまでになかった音楽の本を書いてくれたら嬉しいですね。
取材・文/二階堂 尚