TAG
1969年ウッドストック・フェスティバルエラ・フィッツジェラルドクリームザ・ビートルズビリー・ホリデイモントルー・ジャズ・フェスティバルライブ盤で聴くモントルー
投稿日 : 2023.03.20
文/二階堂尚

MENU
「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。
エラ・フィッツジェラルドは、モントルー・ジャズ・フェスティバルに都合5回出演していて、うち3回分がこれまでCD化されていた。初出演だった1969年のステージは以前にDVD化されたことがあったが、最近ようやく高音質音源としてリリースされた。エラのバックを長年務めた名手トミー・フラナガンのトリオとともにステージに立ったエラは当時52歳、デビューから35年目を迎えた大ベテランだったが、溌溂(はつらつ)とした若々しい歌声と天才的なインプロヴィゼーションのセンスで、欧州のオーディエンスの心を鷲掴みにしたのだった。
1969年という年は、大衆音楽の大きな転換点だった。ビートルズは『アビイ・ロード』をリリースして終息に向けたカウント・ダウンに入り、ローリング・ストーンズはリーダーのブライアン・ジョーンズの脱退と変死を経て次の時代への一歩を踏み出した。レッド・ツェッペリンやキング・クリムゾンのデビュー作、デヴィッド・ボウイの実質的なデビュー・アルバムが発表されたのもこの年である。
アメリカでは8月にウッドストック・フェスティバルが開催され、12月にはストーンズが主催したフリー・コンサートで、「オルタモントの悲劇」と呼ばれる事件が起こった。観客の黒人青年が警備係だったヘルズ・エンジェルスに刺殺された事件である。ロックの幻想と幻滅が同時にやってきた年が1969年であった。

ブラック・ミュージックに目を向ければ、ジェイムズ・ブラウンの『セイ・イット・ラウド・アイム・ブラック・アンド・プラウド』や、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの『スタンド!』など、ファンクの記念碑的な作品がこの年に発表されている。
ジャズにおける一番の「事件」は、マイルス・デイヴィスの『イン・ア・サイレント・ウェイ』のリリースだろう。それまでアルバムごとに一歩ずつエレクトリック化に進んでいたマイルスが、新しい表現へと大きく跳躍したのがこのアルバムだった。この作品が発売された直後に、マイルスはアコースティック・ジャズからの決別を不可逆的なものにした『ビッチェズ・ブリュー』のレコーディングに入っている。この2作品によって、ジャズがすなわちモダン・ジャズであった時代は事実上の終焉を迎えた。1969年はモダン・ジャズにとって終わりの始まりの年であった。

エラ・フィッツジェラルドがモントルー・ジャズ・フェスティバルに初めて出演した1969年とは、そんな激動の年だった。ロック・バンドやジャズ・ミュージシャンは、スタイルや奏法を変えることで音楽の刷新を図ることができる。では、ジャズ・シンガーはどうか。バンド・メンバーを変えるか、アレンジャーを変えるか、歌唱法を変えるか、取り上げる素材を変えるか。ジャズの歌い手が変化を実現する方法はおそらくその4つしかない。あらゆる音楽家に変化が求められたあの時代にあってエラが選んだのは、素材、つまり歌う曲の趣向を変えることだった。

モントルーに出演する前年のアルバム『サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ』で、エラは同時代のヒット曲であるビートルズの「ヘイ・ジュード」とクリームの「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」を取り上げている。アメリカのジャズ市場をおびやかしていた英国ロックの曲をあえて選んだわけである。エラが歌う「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」に関して村上春樹は、彼女は選曲をちょっと間違えたようだと自身の東京FMの番組「村上ラジオ」で言っていた。「それなりにまとまってはいるんだけど、今ひとつピンとこないですよね」と。確かに、ロックの曲をジャズのビッグ・バンド・アレンジで歌うというのは現在の感覚では端的にかなりダサいし、おそらく当時も新しくは感じられなかっただろう。それでも、彼女が時代に挑戦したことは確かだった。
エラはもとより新しいものへの偏見のないシンガーであり、率直に言えば流行好きだった。ビートルズが初めてアメリカに上陸したのは1964年だが、その年にエラは早くも彼らの「キャット・バイ・ミー・ラヴ」をレコーディングしている。リンゴ・スターについて歌った「リンゴ・ビート」という自作曲をリリースしたのもこの年である。これはレイ・チャールズの「ヒット・ザ・ロード・ジャック」を思わせるマイナー・ミディアムのダンス・ナンバーだった。
さらにさかのぼれば、まだ大衆が新しいジャズであるビバップを受け入れていなかった1947年、エラはビバップ・スタイルのコンボを拡張したディジー・ガレスピーのビッグ・バンドのツアーに同行し、ビバップのインプロヴィゼーションを自家薬籠中のものとしている。レコーディングされたその最初の成果が、ガーシュウィン作の「レディ・ビー・グッド」だった。エラがスキャットでビバップ・フレーズを歌ったことで、ビバップは幅広い聴衆に聴かれることになったのだと、彼女の評伝の著者であるジム・ハスキンズは言っている。エラが「ザ・ファースト・レディ・オブ・ソング」と呼ばれるようになったのはこの頃だった。
最近リリースされた1969年のモントルーのライブ盤には14曲が収録されているが、そのうちの8曲が『サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ』からのナンバーである。演奏は、フランク・デ・ラ・ローサのベースとエド・シグペンのドラムから始まり、名手トミー・フラナガンのピアノがそこに重なる。観客の歓声を聴けば、どのタイミングでエラが聴衆の前にあらわれたかがよくわかる。映像がありありと目に浮かぶような幕開けである。
先日亡くなったバート・バカラックの「ディス・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー」、マルチェロ・マストロヤンニとフェイ・ダナウェイ主演の映画『恋人たちの場所』の主題歌、デューク・エリントンの「ラヴ・ユー・マッドリー」、フランシス・レイの「男と女」と次々に畳みかけられる名曲の中にあって、やはり盛り上がるのは「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」と「ヘイ・ジュード」だ。ピアノ・トリオによるシンプルな演奏をバックにしているぶん、前年のスタジオ・バージョンよりも原曲のエッセンスがストレートに感じられ、メロディのフェイクも自由で闊達である。
「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」は、クリームのベーシストだったジャック・ブルースがジミ・ヘンドリックスのライブを見た直後に即効で書いた曲で、当時の英国ロックによく見られたほとんどリフだけで成立しているようなシンプルでブルージーなナンバーである。エラは天性の即興センスでそこに黒人霊歌や「ワーク・ソング」のエレメントを加えて、原曲のブルース・フィーリングを増幅させている。この歌はこう歌うのよ、と英国の若い白人バンドに見せつけているような名唱と言ってよく、村上春樹もこのバージョンを聴けば、さすがエラと感心するのではなかろうか。
アンコールの「スキャット・メドレー」は、アントニオ・カルロス・ジョビンの「ワン・ノート・サンバ」からスタートして、さまざまな曲の旋律や歌詞の断片を次々に取り入れながら、7分半にわたって即興を繰り広げるすさまじいパフォーマンスである。トニー・フラナガン・トリオの対応力にも舌を巻くほかない。
1969年という大きな変化の年を過ぎて、アメリカのジャズ・シーンでは意外にもビッグ・バンドなどのオールド・スタイルのジャズが一時期流行したらしい。ジョン・F・ケネディ、マルコムX、マルティン・ルーサー・キング、ロバート・ケネディといった時代のアイコンが次々に暗殺され、ベトナム戦争が泥沼化していく中で、人々は素朴だった時代へのノスタルジアにかられたのだとジム・ハスキンズは書いている。加えて、「ロックンロールが放埓と素人芸に身を落としていて、洗練されたリスナーたちは新たにプロの精神と技を切望していた」のであり、「エラは数年前から、こうした流行の徴候が見えると主張していた」のだとも。
エラは初ステージののち計4回モントルー・ジャズ・フェスティバルに出演していて、75年、77年、79年のライブはアルバムとして聴くことができる。いずれのライブ盤でも彼女の「プロの精神と技」を味わうことができるが、69年のステージのエネルギーがやはり抜きん出ている。このアルバムは、名高い60年の『ライヴ・イン・ベルリン』と並ぶ名作として今後も聴き継がれていくのではないだろうか。
ビリー・ホリデイとエラ・フィッツジェラルドとサラ・ヴォーンをジャズ・ボーカルの御三家と最初に言い出したのが誰だったかは不明だが、エラはビリーとしばしば比較された。ビリー・ホリデイは偉大なアーティストで、深い井戸から水を汲み上げるように歌ったが、しかし彼女の歌は人を疲れさせる。その点、エラは聴く者をまったく疲れさせない。きっとそれは彼女の天分なのだろう。そんなジャズ評論家の意見をハスキンズは紹介している。ビリーへの評価はおくとしても、エラの歌が聴き手を疲れさせないというのはまさしくそのとおりだと思う。滑稽曲やコミック・ソング、子どもの向けの曲などを総称してノベルティ・ソングという。そのノベルティ・ソングの歌い手としてスタートした彼女は、バラードを歌ってもブルースを歌ってもシリアスになりすぎることはなく、終始朗らかでキュートだった。彼女には確かな「プロの精神と技」があったが、それを誇示することはなく、その歌は彼女がいつも湛えていた微笑みのように自然だった。

ステージに酔っぱらったギャングがナイフをもって近寄ってきたが、エラは一音も外さずに曲を歌い終えた。クラブの騒がしい客を、やはり音をまったく外すことなく歌いながら黙らせた。野外コンサートでたくさんの羽虫が顔に集まってくると、曲の歌詞を「虫が私を悩ませる」と変えて歌って客を喜ばせた──。評伝で紹介されているこれらのエピソードは、彼女のいわば「飾らない技量」を示す逸話のほんの一部である。
歌や演奏の上手さが音楽を魅力的なものにするとは限らない。しかし、エラ・フィッツジェラルドは、「歌が上手い」ということのあらゆる多様なニュアンスを含んで「上手い歌手」だった。ジャズ・ボーカルを聴いたことがない人にジャズ・ボーカルとは何かと問われたら、ただエラの歌を聴かせればよいと思う。
文/二階堂 尚
〈参考文献〉『エラ・フィッツジェラルド』ジム・ハスキンズ著/山田久美子訳(音楽之友社)、「レコード・コレクターズ」2019年5月号(ミュージック・マガジン)
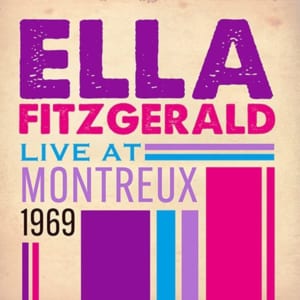
『Live at Montreux 1969』
エラ・フィッツジェラルド
1.Give Me the Simple Life 2.This Girl’s in Love with You 3.I Won’t Dance 4.A Place for Lovers 5.That Old Black Magic 6.Useless Landscape 7.Love You Madly 8.Trouble Is a Man 9.A Man and a Woman 10.Sunshine of Your Love 11.Alright, Okay, You Win 12.Hey Jude 13.Scat Medley 14.A House Is Not a Home
■エラ・フィッツジェラルド(vo)、トミー・フラナガン(p)、フランク・デ・ラ・ローサ(b)、エド・シグペン(ds)
■第3回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1969年6月22日

【モダン・ジャズ・カルテット】不動のメンバーで40年近い活動を続けた不世出のジャズ・コンボ ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.60
投稿日 : 2025.03.17

【ハービー・ハンコック】ドラッグ中毒の渦中で披露した最高のパフォーマンス─ライブ盤で聴くモントルー Vol.59
投稿日 : 2025.01.20 更新日 : 2025.03.13

【リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンド】20数年の時を経て再現されたサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド──ライブ盤で聴くモントルー Vol.58
投稿日 : 2024.11.18

【キング・カーティス&チャンピオン・ジャック・デュプリー】R&B界のトップ・プレイヤーとニューオリンズの巨人の共演──ライブ盤で聴くモントルー Vol.57
投稿日 : 2024.09.16