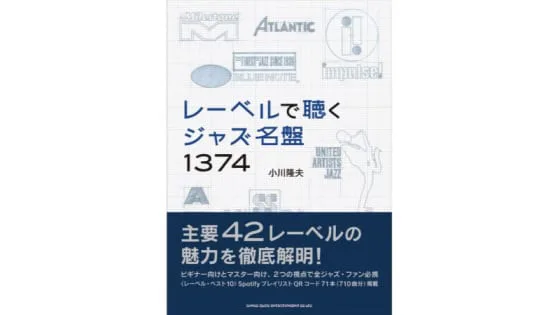投稿日 : 2024.04.19
80年代初頭のNYジャズクラブで何が起きていたのか─小川隆夫 インタビュー

MENU
今から40年ほど前の話だ。小川隆夫は東京医科大の整形外科に勤務していた。医師になって1年が経った頃、ふとしたきっかけで彼はアメリカへの留学を思い立つ。理由はいくつかあった。まずは大好きなジャズを、本場で思う存分聴きたい。さらに、日本の大学病院での激務に嫌気もさしていた。結婚して子供も生まれたばかりだったが、このタイミングが最後の冒険のチャンスだと直感したのだ。
かくしてニューヨーク大学への留学の手はずを整え、1981年に渡米。大学院で2年間学ぶこととなった。医学の勉強に勤しみ、ジャズのライブを存分に楽しみ、子育てに奔走した2年間、彼は日々の出来事を克明に書き残していた。その日記をまとめたのが本書『ジャズ・クラブ黄金時代 NYジャズ日記1981-1983』である。タイトルどおり、ジャズのライブ鑑賞記を中心に構成された “ジャズ日記” だ。

この日記が書かれて40年が経った現在、小川隆夫は医師として、また多くの著作をもつ文筆家として、ときにはジャズミュージシャンのことばを報せるスポークスマンとして活躍している。が、本書に記されるのは “まだ何者でもなかった小川隆夫”の日々である。とは言え、登場人物のあまりの豪華さに、ジャズファンは心躍るはず。さらに、1980年初頭のニューヨークにタイムトラベルするような感覚も楽しい。
著者は当時の日記を読み返し、こうして書籍に整える過程で「あの時代(80年代初頭)が、マンハッタンにおけるジャズクラブ最後の黄金時代だった」ことを実感したという。そこは一体どんな世界だったのか、著者に詳しく話を聞いてみよう。
600本を超えるライブ鑑賞の記録
──この本は、かつて小川さんがつけていた日記をもとに作られた。
そうです。1981年から83年にかけてニューヨークに住んでいた時の記録です。その当時に書いたものを、書籍化にあたって多少は文言を直したりしたけど、基本的にそのまま。新たに何か書いたっていう部分もほとんどなくて、ちょっと補足を入れた程度です。ただ、こんなに厚くなるとは思わなかった。
──少し前に出した『マイルス・デイヴィス大事典』と同じくらいの厚さになりましたね。

今回、もっと分厚くなりそうだったんですよ。当時つけていた日記には、プライベートなこともたくさん記録していて、当初はそれも含めてすべて書き出していった。すると最初の1〜2か月分くらいで相当な文字量になってしまって、これは無理だなと思って。
一応、それら全ての内容も書き起こして清書してみたんですが、その「コンプリート版」を本にしたら、この倍の厚さになってしまいますね。そんなわけで、ジャズにまつわるトピックだけに絞り込んで一冊にまとめました。
──まず、本書の核になっているのは、小川さんが現地で観たライブのレポート。その数(600本超)も驚きですが、それぞれのライブが “いつ、どこで、誰が、どんなメンバーと演奏したのか” など、詳細に記述されているのもすごい。これをまとめるのは大変な作業だったと思うのですが…
そうでもない。まず「どこで何を観て、どうだった」って話が日記に書いてある。で、それとは別に「この日の出演者は誰で、どんな編成だったか」みたいなデータ集を別に作っていた。なおかつ、リファレンス用にインデックスカードみたいなものを作成していて、日付やアルファベットでデータをひけるようにしておいた。

──それら3つのデータが、互いにリンクしている。
そう。他にも、当時のチケットとか広告、パンフレットの類も保存しておいたので、これらの資料やメモと文書を行き来することで、簡単に確認作業や事実の整合が取れるわけです。
──まさか、40年後にこうして本を出すために、そんなデータ集を作っていたわけじゃないですよね。
当時はそんなこと考えもしなかった。これ(データ集づくり)は単に、僕の性分なんです。まあ、いつか見返すこともあるだろうとは思っていたけど、こんな形で世に出すことになるとは思ってもみなかった。
ニューヨーク史上最悪の年に…
──確かに、1981年当時の小川さんは大学院で勉強中の、いわば “ただの学生” だったわけですからね。
そうです。ニューヨーク大学・大学院のリハビリテーション科で学んでいました。
──当時、小川さんは日本の大学病院で医師として勤務していたけど、あるとき留学を決意した。その詳細は本書に書かれていますが、何にせよとんでもない冒険ですよね。日本での医師としてのキャリアを一旦止めて、しかも奥さんと幼い娘さんを連れてニューヨークで生活を開始するなんて。
そうですね(笑)。そのことに関しては、カミさんはいまだに怒ってると思いますよ。あの当時、日本とアメリカは物理的にも心理的にもすごい距離があった。国際電話も高いし、今みたいにEメールでやり取りもできないし、帰るに帰れない。そんな状況で2歳の子供を連れてね。
──1981年といえば「ニューヨークが史上最も犯罪の多かった年」として知られる。
確かに治安は悪かったです。カミさんは一度、スリに遭いました。渡米して早い段階でそんな目にあって、かなり用心して暮らしていたので滞在中の犯罪被害はそれだけで済みました。

──そんな荒廃したニューヨークだけど、小川さんにとってユートピアとも呼べるような世界が、そこにはあった。
当時のニューヨークのジャズシーンは(いわゆるモダンジャズのレジェンドと呼ばれるような)有名な大ベテランと、ウィントン・マルサリスのような注目の若手、さらには僕が全く知らないような新人プレイヤーが混在して、盛んに競演も行われていた。しかも、そういったプレイヤーたちの演奏が、毎日のように近所で繰り広げられている。
──その状況を存分に楽しんだ2年間だった。
いや、そう簡単にはいかなくて。最初の1年は種を蒔いた。そして2年目に収穫をした。そんな印象です。
つまりね、最初の1年は、ニューヨークのジャズ関係者に対して、僕の存在をアピールし続けたんです。とにかくあらゆるところへ顔を出して、できる限りのコミュニケーションを取るように心がけました。そうすることで、効率よくライブの情報が集まると考えたんです。
たとえばライブハウスに行くと、顧客のメーリングリストを作るためにノートや紙が置かれている。そこに必ず自分の名前と住所を書き残すようにした。
──なるほど。ジャズに関する情報が集まるように、方々に種を蒔いたわけですね。
そう、最初の1年はひたすら種蒔きです。まずは自分の存在を知ってもらうためにライブの現場に通って、店の人とか常連客とか出演者とも会話をして、顔と名前と連絡先を知ってもらって。
それが実ったのが2年目。アーティストとか店から「今度こういうライブやりますよ」っていうチラシが送られてきたり、仲間から「今度あそこで誰々がライブやるらしいよ」みたいな情報がどんどん入ってくるようになった。
ジャズ情報収集で英語力UP
──当時、ジャズのライブに関する情報収集は、クチコミとか足で稼ぐしか方法はなかったのでしょうか?
当時の日本には『ぴあ』みたいなエンタメ情報誌があったけど、アメリカにはそういうものがなくて。まあ、『ヴィレッジ・ヴォイス』とか『ニューヨーカーマガジン』のエンターテイメント欄が、紙媒体としては数少ない情報源のひとつでした。
ただ、そうした雑誌に載ってるのは、もっぱらヴィレッジヴァンガードとかブルーノート、スイートベイジルみたいな有名な店の情報なんですね。だから小さなライブハウスで不定期でやってるライブとか、ミュージシャン個人がやってる催しなんかは、なかなか情報が手に入りにくい。
──そういう情報が入ってくるネットワークを、自分で作り上げていったわけですね。
そう、ニューヨークに行って、わりと初期の段階で気がついたのは「情報は自分で取らなきゃいけない」ってことでした。
──いまは当然のように、ウェブで簡単に情報収集できますけども、当時そんな環境はないですからね。
だから、そこに集まる人は、ものすごく熱心なファンなんですよ。自分の力で調べまくって情報源も持っていている人たち。そういうコミュニティと繋がる必要があったわけです。
この本を読んでもらうとわかるんだけど、結構、フリージャズ系のライブにも行ってるんですよ。それって決してコマーシャルなものではないので、本当に好きな人だけが集まるような場なんです。そこにたどり着くには、やはり情報網が大事になってくる。そのネットワーク作りを1年かけてやったような感じですね。もちろん「最初の1年は種まきに専念するぞ」と臨んだわけではなくて、いま振り返ると、結果的にそうだったな、という印象です。
──ただ、そうした振る舞いのおかげで英語力も磨かれたのでは?
じつはそれが最大の収穫だったのかもしれないですね。勉学に活かされたので。
ジャズクラブでレポートを書く学生
──この本のタイトルだけ見ると “小川隆夫が若い頃にニューヨークに行ってジャズのライブを観まくった話” と思われるかもしれませんが、留学生として “猛烈な勉強の日々” でもあったわけですよね。
とにかく勉強して結果を出さないといけない。僕が入ったリハビリテーション科は前期と後期の二期制で、前期のスタートは秋。そこからまずは前期末の試験に向けて勉強する。その間にもレポートを出したり、他にもやることがいっぱいありました。
ちなみに期末の試験はABCDEの5段階で評価されるんだけど、留学生はAかBじゃないと次の期の受講ができない。失敗すると、そこでもうお終いになってしまうんです。Aは無理としてもBは絶対に取らなきゃいけない。だから相当に勉強はしました。
──他にもいろんな採点があるんですよね。
あります。まずは試験とレポート。あとは授業中の質問に対する応えとか、取り組む姿勢や態度なんかを総合して評価されます。僕は試験が不安だったから、それ以外で稼げるだけは稼ごうと思って、授業中はとにかく積極的に質問をして。あとは、とにかくレポートを必死で書いた。
──そのレポートを、もっぱらジャズクラブで書いていたとか。
うん、ジャズクラブへ行くと書ける。今日はどんなライブになるんだろう? そんな期待をしながらレポートに向かうと、不思議なほど集中できるんです。だからジャズクラブっていうのは僕にとっては勉強しに行く場所でもあった。
──喫茶店や図書館じゃダメなんですか?
演奏が始まる前後にジャズクラブで勉強したりレポート書いたりしてると「お前、何やってんだ?」って話しかけてもらえるんです。で、自分の境遇やジャズファンであることを話すと、僕に興味を持ってくれて。そんな会話のついでに、レポートのちょっとした英語の言い回しとか教えてもらったり、いろんな質問もできて書き物もはかどる。そういう意味でも、ジャズクラブはいい場所だった。
──さっき話に出た “種まき” としても有効ですね。
その通り。なんか変なやついるぞ、っていうふうに見てくれて、僕の存在を知ってもらえるわけです。「先週にスイートベイジルで勉強してたやつが、今日はバンガードにもいるぞ」みたいな感じで、ジャズクラブの界隈で認知されるようになっていった。そうやって、お店の人とか、お客、ミュージシャンとの繋がりができていった感じですね。
著名ミュージシャンたちと交流
──ミュージシャンとの交流についても、この本ではいろいろと書かれていますけど、なかでもウィントン・マルサリスは数多く登場する。運命的というか不思議なエピソードもありますね。
ウィントン・マルサリスと知り合って、ライブ終わりに一緒に帰ることになった。なんとなく帰路が同じ方向だったから “途中まで一緒に歩こう” という感じで。すると、どんどん家に近づいてきて、最終的に同じ場所に到着した。じつは隣の建物(アパート)に住んでたっていう。あれは驚いた。

──以来、ウィントンの自宅に招かれたりアドバイスを求められたりと、信頼が深まっていく。ほかにも、アート・ブレイキーやギル・エヴァンスといったレジェンド級の音楽家とプライベートな付き合いが始まったり、在米の日本人ミュージシャン、菊地雅章さんや鈴木良雄さんとも深く交流しますね。
プーさん(菊地雅章)はとにかく顔が広くて、いろんなミュージシャンに信頼されていた人なので、彼を介してどんどん人脈が広がっていったのは確かです。寡黙で、人付き合いがいい方でもないけど、プーさんとジャズクラブに行くと有名人がみんな挨拶に来るし、彼が持っている人脈も情報量もすごかった。本当に不思議な人だったね。
──本書のなかでも「プーさん」の登場率は高いですね。目次にもある「ジャコ(パストリアス)とプーさんが大げんか」という回はハラハラしましたが。他にも、目次には「“伝説”のアートペッパーを目撃」とか「ウィントンにジャケットのアイディアが採用された」「ブレイキーのローディーをやった」「泥酔したデクスター・ゴードンを家まで送った」みたいな文言が並んでいて、なんとも刺激的な日々だったことがわかります。なかでもいちばん衝撃的な出来事は何でしたか?
うーん、いろいろあるけれど、驚いたのは、ステージ上で(ソニー)ロリンズがぶっ倒れたことかな…。強く心に残ったのは、セロニアス・モンクが亡くなって、葬儀に行ったこと。
モンクの死去については、社会的に大きなニュースとして扱われたことにも驚いた。亡くなる数日前から、毎日のようにテレビで情報を流していたし、メジャーなチャンネルがこぞって報道するなんて、ジャズミュージシャンとしてはきわめて稀ですよ。偉大な人だったのだな、と改めて実感しました。
──現地のミュージシャンたちはどんな様子でした?
あのときはニューヨーク中のジャズクラブが喪に服した。あらゆるアーティストがモンクの曲を演奏したし、ジャンルを超えて、たとえばロックのバンドが追悼に参加したり。1か月くらいの間はそんな感じで、ずっとモンクの曲を演奏してる場面に出くわしたから、かなり長いあいだ尾を引いていた印象ですね。かつてチャーリー・パーカーが亡くなった時もそんな様子だったと聞くから、世間的にはパーカーの死と同じくらいのインパクトがあったんだと思います。

──セロニアス・モンクはピバップのパイオニアのひとりですが、その世代の人たちも当時は存命で、現役ミュージシャンとしてライブに出演している人も多くいた。同時に、ウィントンに代表されるような新世代もそこにいて、非常に面白い状況だったわけですよね。
新世代と旧世代がぶつかって、共演もあり、試行錯誤もあり、という感じでしたね。新しい連中は、先人たちに学びつつも “自分たちのフォービート・ジャズをやるんだ” っていう強い意志があり、オールドスクールの人たちもそんな彼らに触発されていた。
要するに、ジャズが変わる、歴史の転換点にいる感じが、すごくあったんだよね。そういうのって、後になってから「あれが変わり目だったね」って思うことはよくあるんだけど、あのとき僕はリアルタイムでそれを感じた。本当に何か歴史が変わってるな、変わりつつあるな、ってすごい肌で感じていたんです。
ストリートの偉人に遭遇
──80年代の初頭ニューヨークって、ジャズだけでなく、パンクやヒップホップをはじめ、アートの分野でも面白い動きがあった。たとえば小川さんの日常のすぐそばで、まだ無名のバスキアやキース・ヘリングが壁に絵を描いていたはずなんです。そのことを想像するとワクワクする。
実際にその場面に出くわしたことあるよ。キース・ヘリングが壁に絵を描いてるところを何度も目撃しました。その時の僕は、彼が誰だか知らないんです。たまに見かけて「ああ、また彼が壁に落書きしてるな…」くらいの認識なんだけど、あとから「あの若者がキースヘリングだったんだ」と知ることになる。

さらに言うと、それとはまた別の系統のグラフティも目につくようになって。僕が日本に帰る3か月くらい前だったかな、ヒップホップ系のグラフティが急にたくさん描かれ始めた。
──ちょうど、映画『ワイルドスタイル』(1983年)が公開されて、拍車がかかったタイミングでしょうかね。
ヒップホップのカルチャーはずっと前から存在していたけど、あのタイミングで急にオーバーグラウンドに浮上した印象です。グラフティもそうだし、公園とか街角でね、巨大なラジカセを抱えて大音量で音楽を流す若者があちこちに現れた。
──先週まで誰もそんなことしていなかったのに(笑)。
そう、本当に急にわっと出たんです。ニューヨークのいたるところで。その出始めを見ましたね。その時は「何なんだ?」と思っていたけれど、数か月後に日本に帰って、それが “ヒップホップカルチャーの大爆発” だった、ってことを知った。
──いい時代に滞在しましたね。
そう、あの本には「最後の黄金時代」って書いたけど、いろんな意味で本当に黄金時代だったと思いますよ。
NYで自己改革─“ジャズ本” を多産
──そうやって新しいムーブメントの発生や、若い才能を目の当たりにした。当の小川さんもまた、何者でもない、これから世に羽ばたこうとする新世代だった。この並立も、本書の面白さだと感じました。
確かにね、これから医師としてどんな道を歩むのかもわからないし、のちに自分がジャズに関する著書を出すなんてことも考えもしなかった。留学先のアメリカで、ただ楽しくてジャズを聴いていただけ。でもこうして振り返ると、あのニューヨークでの体験や出会い、そしてこの日記が、いまの僕の原点なんだと思います。
──確かに、小川さんが文筆家となるきっかけも、このニューヨーク滞在中にありました。
そう、出版社やレコード会社の人と出会って、原稿を依頼されたことから始まった。
──そして気づけば、単著・共著あわせて100冊くらいは書いてきた。最近だと、先述の『マイルス・デイヴィス大事典』を出して、そのすぐあとに『来日ジャズメン全レコーディング 1931–1979 レコードでたどる日本ジャズ発展史』。その次作となるのが本書『ジャズ・クラブ黄金時代 NYジャズ日記1981–1983』。で、その後にもう一冊、ガイドブックを出しましたね。
『決定版 ブルーノート1500シリーズ完全解説』という本です。これはブルーノートレーベルの“1500番台”として知られる1501番から1600番までのラインナップ全99作品を解説したもの。

この本を作ろうと思ったきっかけは、スポティファイとアップルミュージックで1500番台が全部聞ける、ってことに気づいたから。というわけで、作品の解説それぞれに、音源にリンクするQRコードをつけました。
──解説文を読みながらスマホでアルバムも聴ける、という仕様なんですね。
さらに、いまもう一冊書いています。以前に『レーベルで聴くジャズ名盤1374』という本を出したのですが、その続編にあたる本。今回はちょっとマイナーなレーベルに焦点を当てた内容です。
──ものすごい勢いで本を出し続けていますよね。
その積極的な姿勢も、じつはニューヨーク時代に培ったみたいです。自分では気づかなかったけど、アメリカから帰ってきて「性格が変わったね」といろんな人から言われました。
確かに、もともと消極的で引っ込み思案な性格だったんです。ところが、ニューヨークでの2年間、学校では及第点を取るために授業で必死に自分をアピールし、ジャズ界隈でもネットワーク作りのために懸命に動いた。どうやらそれが自分の性格に変化をもたらしたらしい。そういう意味でも、あの日々は “いまの自分” につながる原点なんだと思いますね。