
2024年にリリースされた “ジャズ系” 作品の中から、聴き逃せない50作をセレクト
構成・文/土佐有明
Abdullah Ibrahim/3
 50年代から南アフリカ共和国で活動してきたピアニスト、ダラー・ブランドは、イスラム教に改宗後はアブドゥーラ・イブラヒムと名乗っている。そんな彼が89歳にしてリリースしたロンドンでのライヴの実況盤。フルートやピッコロも吹くサックス奏者とチェロも弾くウッド・ベースとのトリオで、悠々たる中にも緊迫感が漲る演奏が展開される。イブラヒムのピアノはやはり格別で、ベテランならではの芳醇な味わいを醸し出している。
50年代から南アフリカ共和国で活動してきたピアニスト、ダラー・ブランドは、イスラム教に改宗後はアブドゥーラ・イブラヒムと名乗っている。そんな彼が89歳にしてリリースしたロンドンでのライヴの実況盤。フルートやピッコロも吹くサックス奏者とチェロも弾くウッド・ベースとのトリオで、悠々たる中にも緊迫感が漲る演奏が展開される。イブラヒムのピアノはやはり格別で、ベテランならではの芳醇な味わいを醸し出している。
Amaro Freitas/Y’Y
 これをジャズに括っていいのか迷うところだが、ジャズ本来の融通無碍で雑駁な性質を正当に受け継いでいるという意味では、極めてジャズ的だと言えるだろう。ブラジル出身のピアニストが、自然や先住民をテーマに作った楽曲が並んでおり、現実音や具体音がピアノと並列に違和感なく共存している。その根底にはアマゾン流域で過ごした体験が眠っているそうで、人智を超えたスケールの大きさと悠久の時の流れに圧倒される。
これをジャズに括っていいのか迷うところだが、ジャズ本来の融通無碍で雑駁な性質を正当に受け継いでいるという意味では、極めてジャズ的だと言えるだろう。ブラジル出身のピアニストが、自然や先住民をテーマに作った楽曲が並んでおり、現実音や具体音がピアノと並列に違和感なく共存している。その根底にはアマゾン流域で過ごした体験が眠っているそうで、人智を超えたスケールの大きさと悠久の時の流れに圧倒される。
Answer to remember/Answer to rememberⅡ
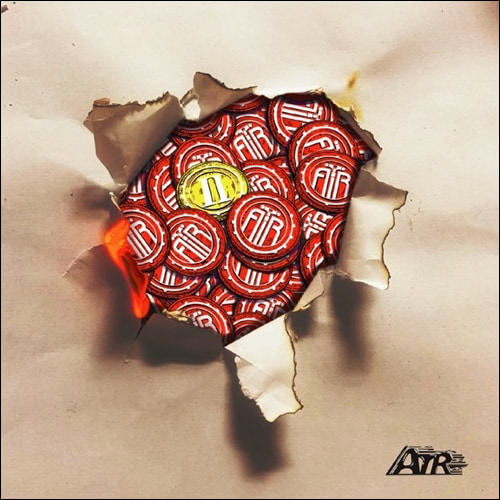 ジャズ畑出身ながら昨今はくるりや椎名林檎のバンドでもドラムを叩く石若駿。彼を中心としたプロジェクトの2作目は、マーティ・ホロベックやMELRAWらを迎えたもりだくさんの内容。中学生の時に日野皓正のバンド・メンバーに抜擢された石若のラウドで野趣に富むドラムを軸に、KID FRESINOのラップやトモキ・サンダースのサックスなどが華を添える。石若自身によるピアノの弾き語りで幕を閉じるのも、美しい余韻を残すニクい演出だ。ソングライターとしての彼の才能も感じ取れる。
ジャズ畑出身ながら昨今はくるりや椎名林檎のバンドでもドラムを叩く石若駿。彼を中心としたプロジェクトの2作目は、マーティ・ホロベックやMELRAWらを迎えたもりだくさんの内容。中学生の時に日野皓正のバンド・メンバーに抜擢された石若のラウドで野趣に富むドラムを軸に、KID FRESINOのラップやトモキ・サンダースのサックスなどが華を添える。石若自身によるピアノの弾き語りで幕を閉じるのも、美しい余韻を残すニクい演出だ。ソングライターとしての彼の才能も感じ取れる。
Austin Peralta/Endless Planets(Delux Edition)
 22歳で惜しまれながら急逝したピアニストの2枚組アルバム。2011年にリリースされた『エンドレス・プラネッツ』と、BBCのスタジオで録音されたライヴ盤から成る。前者はベン・ウェンデルの天空を掛けるようなダイナミックなサックスが、後者ではリチャード・スペイヴンのマシーナリーなビートが際立つ。マッコイ・タイナーからの影響を窺わせるペラルタのピアノは、清冽で瑞々しいことこのうえない。
22歳で惜しまれながら急逝したピアニストの2枚組アルバム。2011年にリリースされた『エンドレス・プラネッツ』と、BBCのスタジオで録音されたライヴ盤から成る。前者はベン・ウェンデルの天空を掛けるようなダイナミックなサックスが、後者ではリチャード・スペイヴンのマシーナリーなビートが際立つ。マッコイ・タイナーからの影響を窺わせるペラルタのピアノは、清冽で瑞々しいことこのうえない。
馬場智章/ELECTRIC RIDER
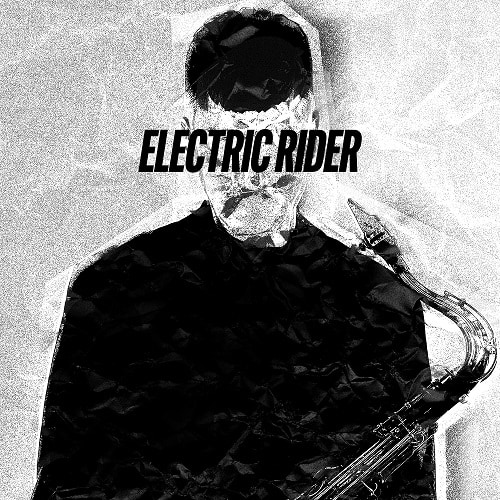 これまでオーセンティックなジャズを奏でていた印象の馬場智章だが、本作で一気に化けた。BIGYUKIを共同プロデューサーに迎え、エレクトリックでダンサブルな作品に。驚いたリスナーも多いだろう。いわゆる“ジャズ・アルバム”のようなものは絶対につくらない、と決めて制作に臨んだそうだが、その意気やよし。サイケやダブを連想させる特異な音響設計、フロアを意識したサウンドメイクが功を奏し、進取の精神に富むアルバムとなっている。映画『BLUE GIANT』でも演奏を担当したサックスも好調。
これまでオーセンティックなジャズを奏でていた印象の馬場智章だが、本作で一気に化けた。BIGYUKIを共同プロデューサーに迎え、エレクトリックでダンサブルな作品に。驚いたリスナーも多いだろう。いわゆる“ジャズ・アルバム”のようなものは絶対につくらない、と決めて制作に臨んだそうだが、その意気やよし。サイケやダブを連想させる特異な音響設計、フロアを意識したサウンドメイクが功を奏し、進取の精神に富むアルバムとなっている。映画『BLUE GIANT』でも演奏を担当したサックスも好調。
Brad Mehldau/After BachⅡ
 ブラッド・メルドー(p)による、バッハを題材にしたアルバムの第二弾。バッハの曲とメルドーのオリジナルと即興演奏によって構成されており、偉大なる先達に敬意を払いながらも、自らの解釈を発揮して、優美で慎ましやかな旋律を奏でている。感情の昂ぶりや起伏をオブラートにつつんでそっと差し出すようなタッチはメルドーならでは。抑揚のある展開で最後まで飽きさせずに聴かせてくれる。なお、クラシックの偉人ガブリエル・フォーレをテーマにしたアルバムも同時発売された。
ブラッド・メルドー(p)による、バッハを題材にしたアルバムの第二弾。バッハの曲とメルドーのオリジナルと即興演奏によって構成されており、偉大なる先達に敬意を払いながらも、自らの解釈を発揮して、優美で慎ましやかな旋律を奏でている。感情の昂ぶりや起伏をオブラートにつつんでそっと差し出すようなタッチはメルドーならでは。抑揚のある展開で最後まで飽きさせずに聴かせてくれる。なお、クラシックの偉人ガブリエル・フォーレをテーマにしたアルバムも同時発売された。
Chris Potter/Eagle’s Point
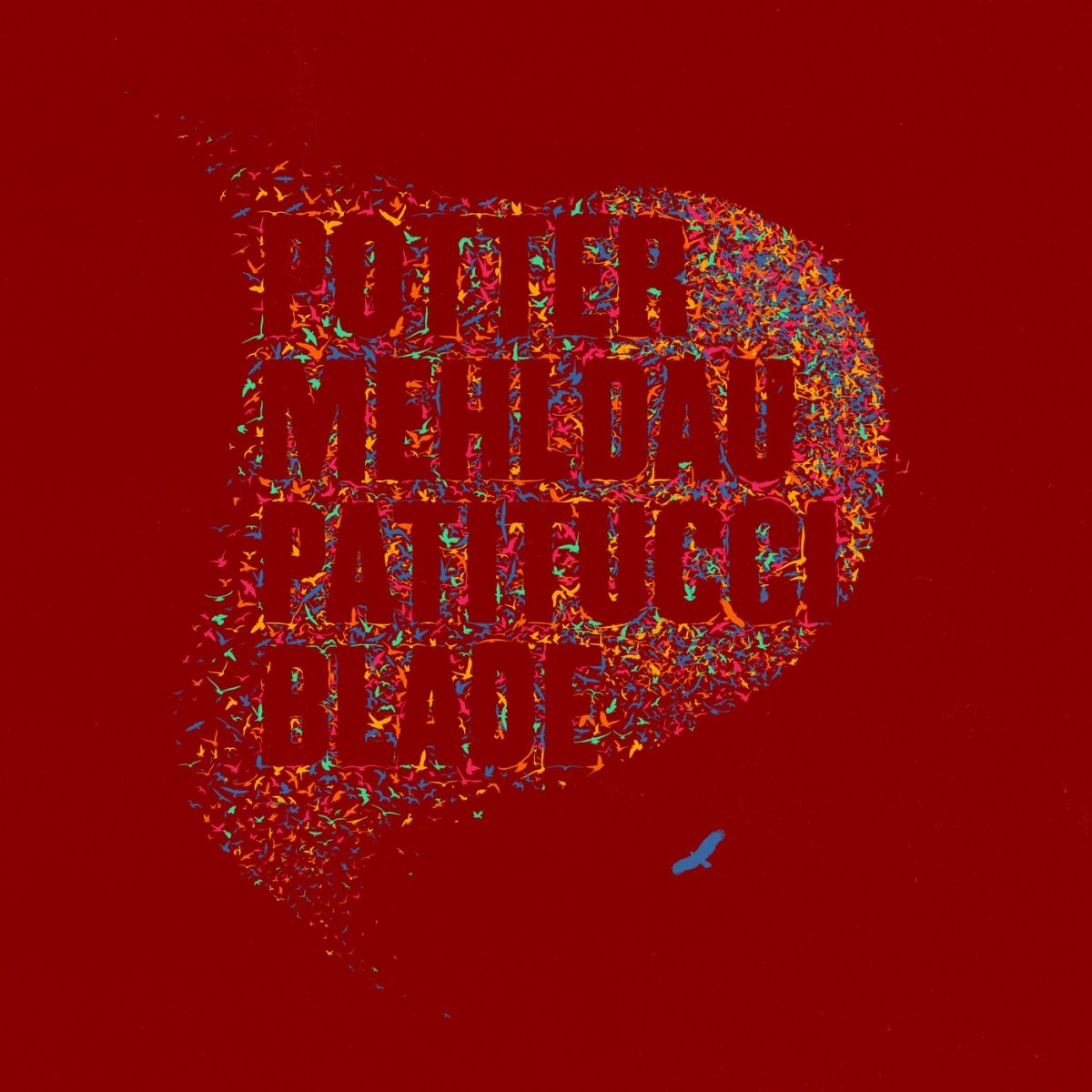 クリス・ポッターっていいなあ、やっぱり、いい。そんな溜息が漏れてしまうほど、このサックス奏者の作品は質が安定している。ブラッド・メルドー(p)、ジョン・パティトゥッチ(b)、ブライアン・ブレイド(ds)という兵とのカルテットで、ポッターはバス・クラリネットとソプラノ・サックスも器用に吹きこなす。伸びやかでハリのあるポッターのプレイは、スティーリー・ダンの作品に参加した時から不変である。
クリス・ポッターっていいなあ、やっぱり、いい。そんな溜息が漏れてしまうほど、このサックス奏者の作品は質が安定している。ブラッド・メルドー(p)、ジョン・パティトゥッチ(b)、ブライアン・ブレイド(ds)という兵とのカルテットで、ポッターはバス・クラリネットとソプラノ・サックスも器用に吹きこなす。伸びやかでハリのあるポッターのプレイは、スティーリー・ダンの作品に参加した時から不変である。
Colin Vallon/Samares
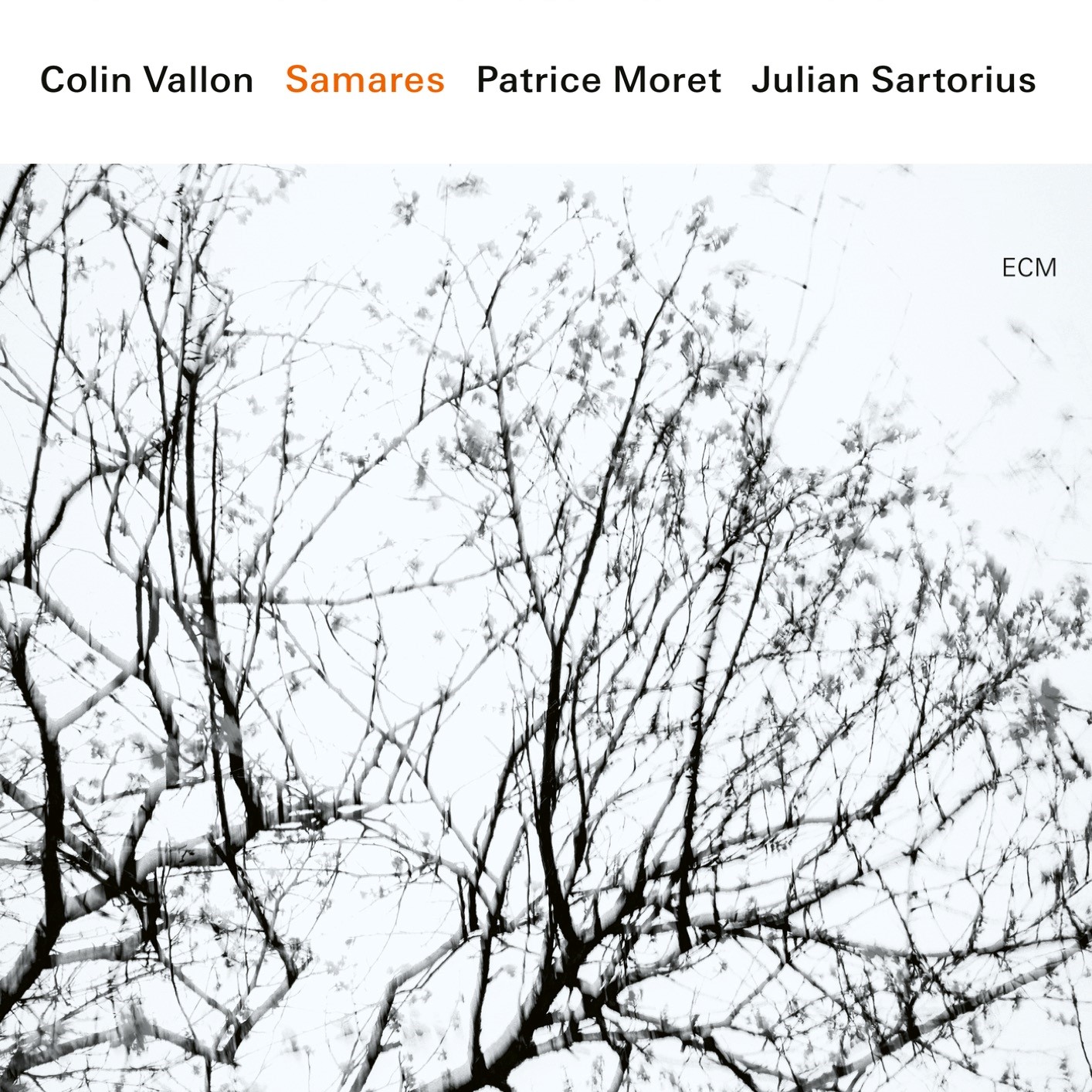 スイス出身のピアニストの7年ぶりとなるアルバムは、前作同様のトリオ編成で、アンチ・ドラマティック、アンチ・スウィングとも言えるミニマルで静謐なサウンドスケープを描き出す。プリペアード奏法を要所で駆使し、エレクトロニクスも随時導入するなど、音響としての美しさと麗しさを前面に押し出した行き方は、ECMから出て然るべき作品という感触だ。このレーベルらしいアートワークも含め、端正で気品に満ちた一枚。リズム隊の控え目ながらツボを押さえたサポートも秀逸だ。
スイス出身のピアニストの7年ぶりとなるアルバムは、前作同様のトリオ編成で、アンチ・ドラマティック、アンチ・スウィングとも言えるミニマルで静謐なサウンドスケープを描き出す。プリペアード奏法を要所で駆使し、エレクトロニクスも随時導入するなど、音響としての美しさと麗しさを前面に押し出した行き方は、ECMから出て然るべき作品という感触だ。このレーベルらしいアートワークも含め、端正で気品に満ちた一枚。リズム隊の控え目ながらツボを押さえたサポートも秀逸だ。
Emile Mosseri & Sam Gendel/Hardy Boys
 今年はサム・ウィルクスとの共演盤もリリースしたサックス奏者のサム・ゲンデルは、頻繁に来日し、折坂悠太や岡田拓郎の作品にも参加する才人だが、こちらのほうが出来は良いのでは? 本作はNYのザ・ディグというバンドに在籍した経歴を持ち、テレビや映画の仕事もこなすエミール・モッセーリとの共演盤、白昼夢を見ているようなアンビエントっぽさが全体を覆いつつも、生の質感を活かしたゲンデルのふくよかなサックスが味わえる。ナラ・シネフロのアルバムと並べて聴いて欲しい逸品。
今年はサム・ウィルクスとの共演盤もリリースしたサックス奏者のサム・ゲンデルは、頻繁に来日し、折坂悠太や岡田拓郎の作品にも参加する才人だが、こちらのほうが出来は良いのでは? 本作はNYのザ・ディグというバンドに在籍した経歴を持ち、テレビや映画の仕事もこなすエミール・モッセーリとの共演盤、白昼夢を見ているようなアンビエントっぽさが全体を覆いつつも、生の質感を活かしたゲンデルのふくよかなサックスが味わえる。ナラ・シネフロのアルバムと並べて聴いて欲しい逸品。
Ethan Iverson/Technically Acceptable
 ブルーノートからのリリースとなる、元ザ・バッド・プラスのピアニストのリーダー作。トーマス・モーガン(b)とクシュ・アバデイ(ds)、シモン・ウィルソン(b)とヴィニー・スペラッツァ(ds)という2組のリズム隊が参加しており、ラグタイムやブギウギからフリー・ジャズまでを変幻自在にこなすピアノは快調に飛ばしまくる。クローザーではピアノ・ソナタの初演まで収録。彼がセロニアス・モンクやジェイソン・モランの系譜に連なるピアニストだと再確認させられた。
ブルーノートからのリリースとなる、元ザ・バッド・プラスのピアニストのリーダー作。トーマス・モーガン(b)とクシュ・アバデイ(ds)、シモン・ウィルソン(b)とヴィニー・スペラッツァ(ds)という2組のリズム隊が参加しており、ラグタイムやブギウギからフリー・ジャズまでを変幻自在にこなすピアノは快調に飛ばしまくる。クローザーではピアノ・ソナタの初演まで収録。彼がセロニアス・モンクやジェイソン・モランの系譜に連なるピアニストだと再確認させられた。
Ezra Collective/ Dance, No One’s Watching
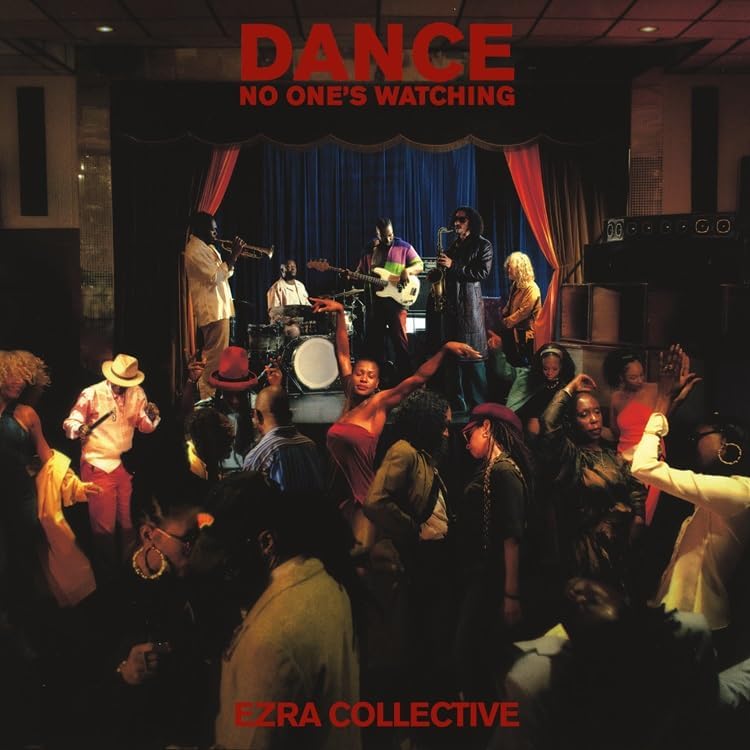 ジャズ・アーティストとしては初めてマーキュリー・プライズを獲得したUKの5人組のアルバム。肉感的で引き締まったグルーヴが全編を覆っており、ファンクやソウルからアフロビーツまでを自然に採用。陽気でポジティヴなヴァイブレーションで満たされた一枚となっている。ポリリズムを駆使する場面があったり、女性シンガー・ソングライターのヤスミン・レイシーが4曲で参加したりと、トピックはさまざま。耳ざわりが良く親しみやすいのでジャズ初心者にも自信をもってお薦めできる。
ジャズ・アーティストとしては初めてマーキュリー・プライズを獲得したUKの5人組のアルバム。肉感的で引き締まったグルーヴが全編を覆っており、ファンクやソウルからアフロビーツまでを自然に採用。陽気でポジティヴなヴァイブレーションで満たされた一枚となっている。ポリリズムを駆使する場面があったり、女性シンガー・ソングライターのヤスミン・レイシーが4曲で参加したりと、トピックはさまざま。耳ざわりが良く親しみやすいのでジャズ初心者にも自信をもってお薦めできる。
Fred harsh/Silent, Listening
 タイトルが最も雄弁に内容を物語っているだろう。ECMからのリリースというのも納得だ。エスペランサ・スポルディングとのデュオでライヴ盤もリリースしたピアニストの独演盤は、厳粛としたリリシズムに満ちた静謐な一枚。スイスのルガーノ・スタジオで録音され、同地の清廉な空気をたっぷり吸いこんだような瑞々しい音世界が繰り広げられている。11曲中4曲がスタンダードだが、彼の手によるオリジナルのほうが、作曲家としての非凡さが表出していて断然いい。間の取り方も絶妙だ。
タイトルが最も雄弁に内容を物語っているだろう。ECMからのリリースというのも納得だ。エスペランサ・スポルディングとのデュオでライヴ盤もリリースしたピアニストの独演盤は、厳粛としたリリシズムに満ちた静謐な一枚。スイスのルガーノ・スタジオで録音され、同地の清廉な空気をたっぷり吸いこんだような瑞々しい音世界が繰り広げられている。11曲中4曲がスタンダードだが、彼の手によるオリジナルのほうが、作曲家としての非凡さが表出していて断然いい。間の取り方も絶妙だ。
藤井郷子カルテット/ドッグ・デイズ・オブ・サマー
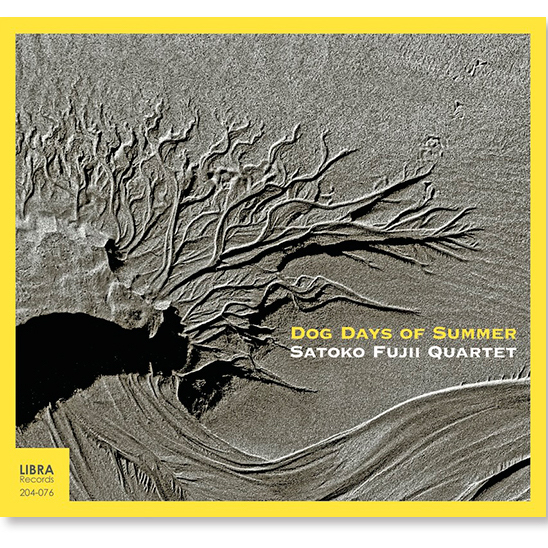
ポール・ブレイに師事した経歴を持ち、過剰なまでの多作家としても知られるピアニストの藤井郷子が、田村夏樹(tp)、早川岳晴(b)、吉田達也(ds)と組んでいるカルテットの15年ぶりのアルバム。レッド・ツェッペリンがフリー・ジャズに挑んだような、という言い方は誤解も招くかもしれないが、それくらい筋肉質でロッキッシュなグルーヴが全体を貫いているということだ。特に、変拍子を織り交ぜながらも(おそらく)シレっとした顔で叩きまくる吉田達也のドラムが凄まじい。
Giovanni Guidi/A New Day
 エンリコ・ラヴァとの共演歴もあるイタリアのピアニストの5枚目のリーダー作。静けさの中に張り詰めた緊迫感が漲るサウンドはまさにECM印。沈黙の次に美しい音楽とは、こういう作品のことを言うのだろう。特筆すべきは今もっとも注目すべきサックス奏者のジェームス・ブランドン・ルイスが参加していること。彼のプレイが全体の牽引役になり、アルバムに幅と膨らみをもたらしている。ジョヴァンニのピアノはブランドンを後押しするようにロマンティックなフレーズを繰り出してくる。
エンリコ・ラヴァとの共演歴もあるイタリアのピアニストの5枚目のリーダー作。静けさの中に張り詰めた緊迫感が漲るサウンドはまさにECM印。沈黙の次に美しい音楽とは、こういう作品のことを言うのだろう。特筆すべきは今もっとも注目すべきサックス奏者のジェームス・ブランドン・ルイスが参加していること。彼のプレイが全体の牽引役になり、アルバムに幅と膨らみをもたらしている。ジョヴァンニのピアノはブランドンを後押しするようにロマンティックなフレーズを繰り出してくる。
GoGo Penguin/From The North – GoGo Penguin Live In Manchester
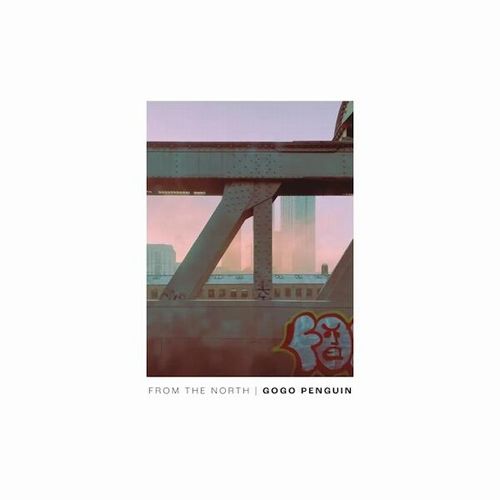 マンチェスター出身の3人組のライヴ盤。ドラマーがロブ・ターナーからジョン・スコットに交替してから初めての音源だが、その成果が如実に出ている印象だ。手数が多く重層的なアンサンブルを得意としていたロブと較べると、ジョンはしなやかで柔らかなプレイが特徴。ドラムンベースやダブステップ、ベース・ミュージックからの影響をジャズに落とし込む手法は過去同様だが、機械的なビートが際立った過去作と較べると、有機的で生っぽいテクスチャーが印象に残る。転機となるアルバムだろう。
マンチェスター出身の3人組のライヴ盤。ドラマーがロブ・ターナーからジョン・スコットに交替してから初めての音源だが、その成果が如実に出ている印象だ。手数が多く重層的なアンサンブルを得意としていたロブと較べると、ジョンはしなやかで柔らかなプレイが特徴。ドラムンベースやダブステップ、ベース・ミュージックからの影響をジャズに落とし込む手法は過去同様だが、機械的なビートが際立った過去作と較べると、有機的で生っぽいテクスチャーが印象に残る。転機となるアルバムだろう。
Gregory Privat/Phoenix
 フランスの海外県であるマルティニーク生まれで、マラヴォワへの参加でも知られるピアニスト、グレゴリー・プリヴァ。フランスでジャンゴ・ラインハルト賞を受賞した彼が、20年の『ソーレイ』と同様のメンバーで臨んだトリオ作。スピリチュアル・ジャズをオルタナティヴ・ロック以降の音圧とヒップホップ以降のタイム感でアップデートしたような作風で、饒舌で雄弁なグレゴリーのピアノも磨きがかかっている。エネルギッシュでアグレッシヴなリズム隊は背後から煽り立てるかのようだ。
フランスの海外県であるマルティニーク生まれで、マラヴォワへの参加でも知られるピアニスト、グレゴリー・プリヴァ。フランスでジャンゴ・ラインハルト賞を受賞した彼が、20年の『ソーレイ』と同様のメンバーで臨んだトリオ作。スピリチュアル・ジャズをオルタナティヴ・ロック以降の音圧とヒップホップ以降のタイム感でアップデートしたような作風で、饒舌で雄弁なグレゴリーのピアノも磨きがかかっている。エネルギッシュでアグレッシヴなリズム隊は背後から煽り立てるかのようだ。
Immanuel Wilkins/Blues Blood
 ミシェル・ンデゲオチェロを共同プロデューサーに迎えたアルト奏者の3作目。アルバム・タイトルはbruise(痣)とbluesをかけているのだろう。メロディアスで柔和な響きのサックスは天にも昇る心地よさで、アルバムの穏やかながら艶っぽいトーンをしるしづけている。サックス吹きとしてようやく正当に評価される時がきたか。セシル・マクロリン・サルヴァント、ガナヴィヤなどヴォーカリストもフィーチャーされており、これらの歌ものではミシェルのミュージシャンシップが発揮されている。
ミシェル・ンデゲオチェロを共同プロデューサーに迎えたアルト奏者の3作目。アルバム・タイトルはbruise(痣)とbluesをかけているのだろう。メロディアスで柔和な響きのサックスは天にも昇る心地よさで、アルバムの穏やかながら艶っぽいトーンをしるしづけている。サックス吹きとしてようやく正当に評価される時がきたか。セシル・マクロリン・サルヴァント、ガナヴィヤなどヴォーカリストもフィーチャーされており、これらの歌ものではミシェルのミュージシャンシップが発揮されている。
Jeff Parker, ETA IVtet/The Way Out of Easy
 トータスのメンバーのジェフ・パーカー、ミシェル・ンデゲオチェロやマカヤ・マクレイヴンの作品で重責を担うジョシュ・ジョンソン(as)らによるカルテットのファースト・アルバム。LAのライヴハウスで16年からライヴを続けてきたとあって、その演奏は阿吽の呼吸の上に成り立っている。今様スピリチュアル・ジャズで魅了したかと思うと、ドラムにダブ処理を施すなどして、汲めども尽きぬアイディアの宝庫といった趣。ジム・ホールにも通じるジェフのソロがまた秀抜だ。
トータスのメンバーのジェフ・パーカー、ミシェル・ンデゲオチェロやマカヤ・マクレイヴンの作品で重責を担うジョシュ・ジョンソン(as)らによるカルテットのファースト・アルバム。LAのライヴハウスで16年からライヴを続けてきたとあって、その演奏は阿吽の呼吸の上に成り立っている。今様スピリチュアル・ジャズで魅了したかと思うと、ドラムにダブ処理を施すなどして、汲めども尽きぬアイディアの宝庫といった趣。ジム・ホールにも通じるジェフのソロがまた秀抜だ。
Jenny Scheinman/All Species Parade
 ジャズ・ヴァイオリン奏者としてはレジーナ・カーターを超える逸材ではないだろうか。そう思わせるジェニー・シェイマンの5年ぶりのアルバムだ。以前からアメリカーナの系譜に連なる作風で知られていたが、本作でも、ビル・フリゼールやジュリアン・ラージといったその筋のギタリストを起用。ノラ・ジョーンズ『カム・アウェイ・ウィズ・ミー』にも共に参加したトニー・シェア(b)とケニー・ウォルセン(ds)をリズム隊に迎え、ルーツ・ミュージック色濃厚な世界を繰り広げている。
ジャズ・ヴァイオリン奏者としてはレジーナ・カーターを超える逸材ではないだろうか。そう思わせるジェニー・シェイマンの5年ぶりのアルバムだ。以前からアメリカーナの系譜に連なる作風で知られていたが、本作でも、ビル・フリゼールやジュリアン・ラージといったその筋のギタリストを起用。ノラ・ジョーンズ『カム・アウェイ・ウィズ・ミー』にも共に参加したトニー・シェア(b)とケニー・ウォルセン(ds)をリズム隊に迎え、ルーツ・ミュージック色濃厚な世界を繰り広げている。
Joe Sanders/Parallels
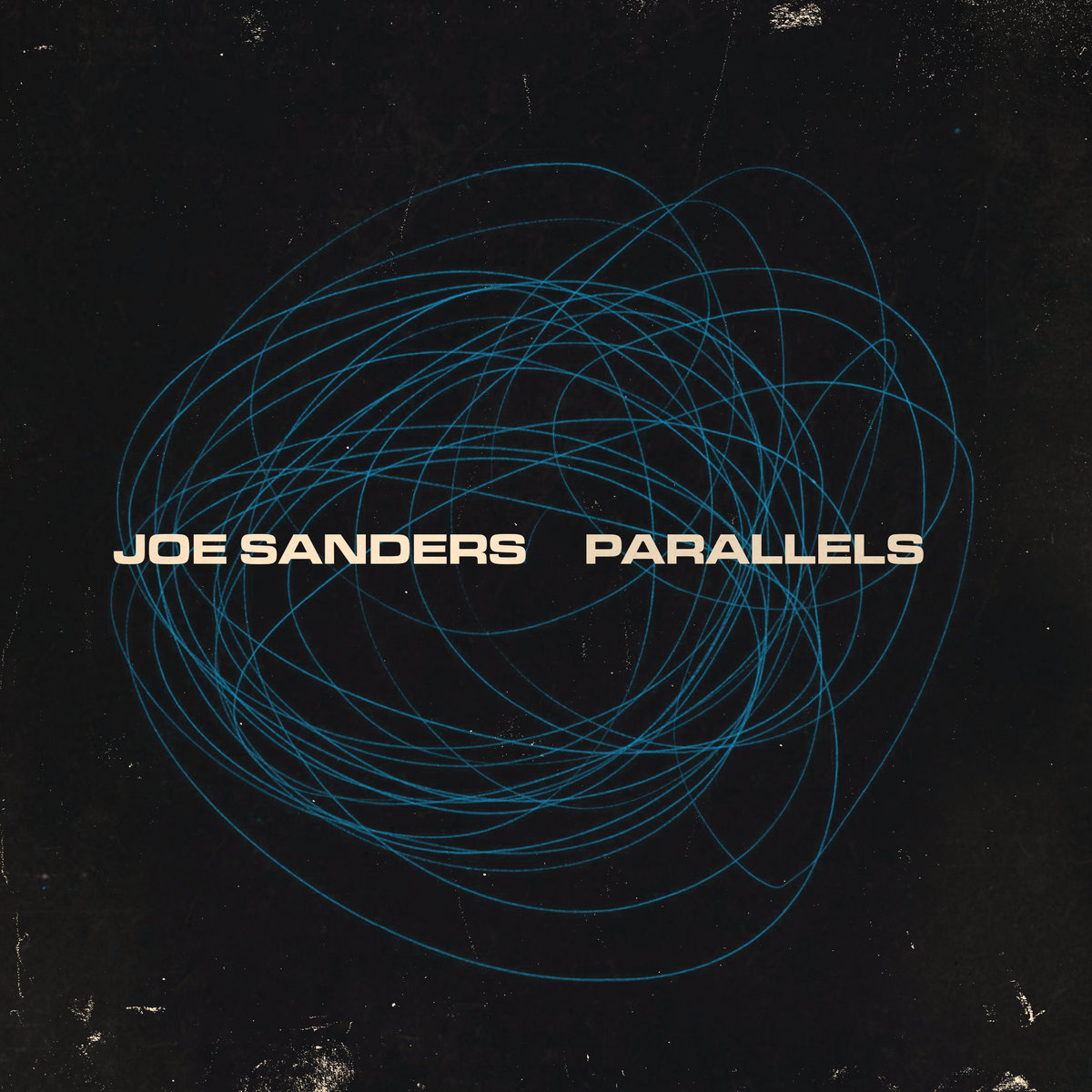 ケンドリック・スコット、ウォルター・スミス3世、シオ・クローカーらと共演歴のあるNYのベーシストのリーダー作。ローガン・リチャードソンの豪放なサックスやグレッグ・ハッチンソンのひらめきに満ちたドラムを推進力に、ストレートアヘッドながらもアイディア豊富な演奏を聴かせる。ソングライティングの能力はもちろん、ベーシストとしても秀でたもののある人で、野太い音色とシンプルなフレージングはリンダ・メイ・ハン・オーにも匹敵する。まだ3作目だが有望株と見た。
ケンドリック・スコット、ウォルター・スミス3世、シオ・クローカーらと共演歴のあるNYのベーシストのリーダー作。ローガン・リチャードソンの豪放なサックスやグレッグ・ハッチンソンのひらめきに満ちたドラムを推進力に、ストレートアヘッドながらもアイディア豊富な演奏を聴かせる。ソングライティングの能力はもちろん、ベーシストとしても秀でたもののある人で、野太い音色とシンプルなフレージングはリンダ・メイ・ハン・オーにも匹敵する。まだ3作目だが有望株と見た。
Jose James/1978
 名ヴォーカリストが足かけ5年を費やして制作したというアルバムは、70年代後期のソウルに触発されたそう。マーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、プリンスからの影響が滲むが、それらを完全に自家薬籠中のものとし、その先へと足を踏み入れた印象。ヴォーカリストとして一皮むけたと言って差し支えないだろう。テリ・リン・キャリントンに師事した経験を持つジャリス・ヨークリーのドラム、ジミ・ヘンドリクスを敬愛するマーカス・マチャードのギターが冴え渡っている。
名ヴォーカリストが足かけ5年を費やして制作したというアルバムは、70年代後期のソウルに触発されたそう。マーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、プリンスからの影響が滲むが、それらを完全に自家薬籠中のものとし、その先へと足を踏み入れた印象。ヴォーカリストとして一皮むけたと言って差し支えないだろう。テリ・リン・キャリントンに師事した経験を持つジャリス・ヨークリーのドラム、ジミ・ヘンドリクスを敬愛するマーカス・マチャードのギターが冴え渡っている。
Josh Johnson/Unusual Object
 ミシェル・ンデゲオチェロのブルーノート発の作品をプロデュースした、シカゴ出身のサックス奏者のアルバム。多重録音を駆使したのだろう、プログラミングされたビートや電子音と自身のサックスが混じり合い、ジャズとミニマル・テクノとエレクトロニカを折衷したような先鋭的な作品に仕上げている。サックスの鳴りや響きの良さは過去最高で、オーネット・コールマンを連想させる瞬間もたびたび。アドリブが続いても決して一本調子にならないところにプレイヤーとしての進化を感じる。
ミシェル・ンデゲオチェロのブルーノート発の作品をプロデュースした、シカゴ出身のサックス奏者のアルバム。多重録音を駆使したのだろう、プログラミングされたビートや電子音と自身のサックスが混じり合い、ジャズとミニマル・テクノとエレクトロニカを折衷したような先鋭的な作品に仕上げている。サックスの鳴りや響きの良さは過去最高で、オーネット・コールマンを連想させる瞬間もたびたび。アドリブが続いても決して一本調子にならないところにプレイヤーとしての進化を感じる。
Julian Large /Speak To Me
 アメリカーナの系譜を探求してきたジョー・ヘンリーがプロデュースしたアルバム。ホルヘ・ローダー(b)、デイヴ・キング(ds)、クリス・デイヴィス(p)の他、ヘンリーの盟友であるパトリック・ウォーレン(key)らが脇を固め、ラージはギターを使って戦前のアメリカ音楽に新たな息吹を吹き込んでゆく。ブルースもカントリーもフォークも溶け込んだ滋養溢れるスープのような音楽であり、今、こんなルーツ指向の作品をつくれるのはビル・フリゼールとラージぐらいだろうと痛感させられる。
アメリカーナの系譜を探求してきたジョー・ヘンリーがプロデュースしたアルバム。ホルヘ・ローダー(b)、デイヴ・キング(ds)、クリス・デイヴィス(p)の他、ヘンリーの盟友であるパトリック・ウォーレン(key)らが脇を固め、ラージはギターを使って戦前のアメリカ音楽に新たな息吹を吹き込んでゆく。ブルースもカントリーもフォークも溶け込んだ滋養溢れるスープのような音楽であり、今、こんなルーツ指向の作品をつくれるのはビル・フリゼールとラージぐらいだろうと痛感させられる。
Julius Rodriguez/Evergreen
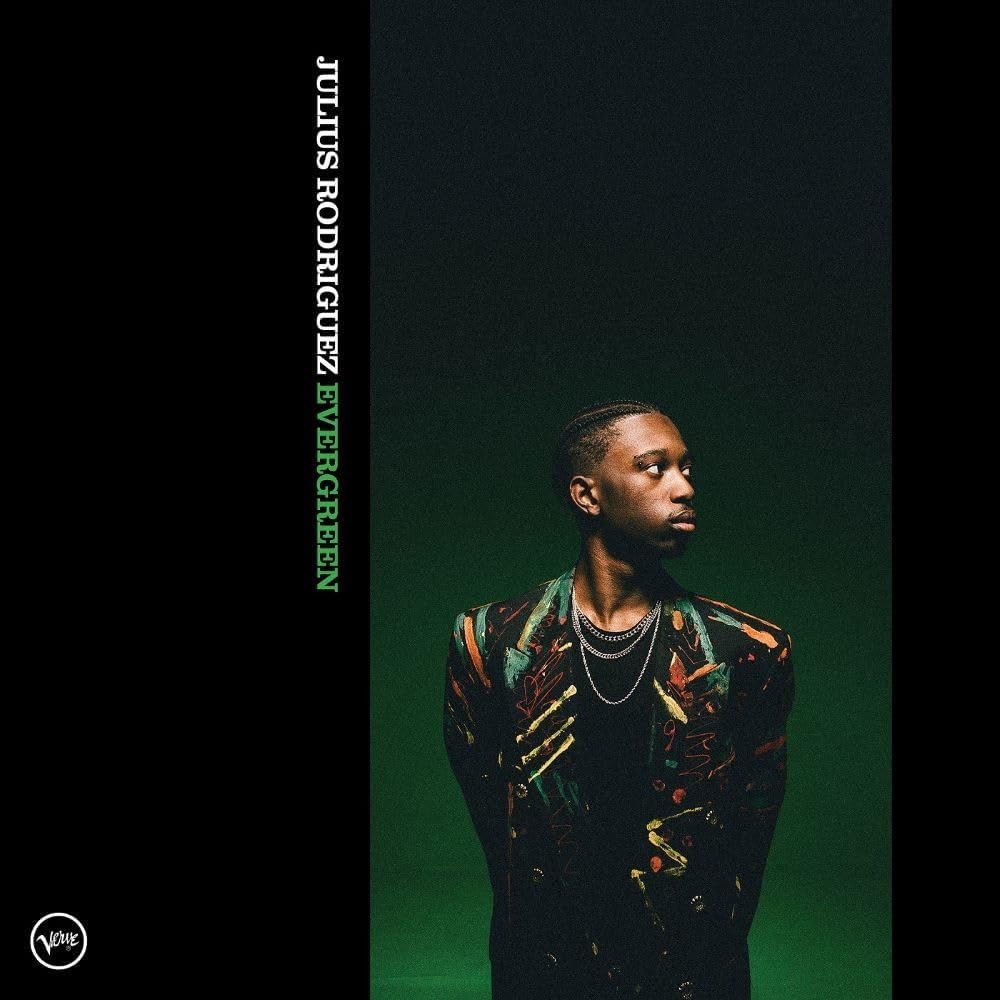 ソランジュなどを手掛けたティム・アンダーソンがプロデュースを担当した2作目。エイサップ・ロッキーのツアーに帯同する一方で、カントリーのアルバムに参加するなど、幅広い音楽性を誇るピアニスト/ドラマー/作曲家の彼だが、本作は意外にもオーソドックス。ヒップホップ以降の感覚をナチュラルに持ちながらも、それをあくまでも気負うことなくジャズのフォーマットに落とし込んでいる。ゴスペルやR&B、フォークやソウルなどの要素も煮詰めた雑多で多面的なサウンドが愉しめる一枚だ。
ソランジュなどを手掛けたティム・アンダーソンがプロデュースを担当した2作目。エイサップ・ロッキーのツアーに帯同する一方で、カントリーのアルバムに参加するなど、幅広い音楽性を誇るピアニスト/ドラマー/作曲家の彼だが、本作は意外にもオーソドックス。ヒップホップ以降の感覚をナチュラルに持ちながらも、それをあくまでも気負うことなくジャズのフォーマットに落とし込んでいる。ゴスペルやR&B、フォークやソウルなどの要素も煮詰めた雑多で多面的なサウンドが愉しめる一枚だ。
Kamasi Washington/Fearless Movement
 サンダーキャット(b)、テラス・マーティン(as)、ジョージ・クリントン(vo)ら豪華ゲストを迎えた2枚組。カマシ本人によると、本作のテーマは“ダンス”とのことだが、躍動的で肉感的なグルーヴが脈打っているのは間違いない。音楽的にはこれまでどおり今様スピリチュアル・ジャズを基軸としながらも、ビート・ミュージックやファンク、ラテン音楽などの要素が付加されている。それでいて、前作よりもポップで親しみやすい作品に仕上がっているのが面白い。野太いサックスも絶好調だ。
サンダーキャット(b)、テラス・マーティン(as)、ジョージ・クリントン(vo)ら豪華ゲストを迎えた2枚組。カマシ本人によると、本作のテーマは“ダンス”とのことだが、躍動的で肉感的なグルーヴが脈打っているのは間違いない。音楽的にはこれまでどおり今様スピリチュアル・ジャズを基軸としながらも、ビート・ミュージックやファンク、ラテン音楽などの要素が付加されている。それでいて、前作よりもポップで親しみやすい作品に仕上がっているのが面白い。野太いサックスも絶好調だ。
Keyon Harrold /Forever Land
 ビヨンセ、ジェイ・Z、エミネム、ディアンジェロ、キース・リチャーズらと共演/録音歴のある、LA在住のトランペッターのソロ作。「愛、平和、理解」といったテーマを彼なりに咀嚼した本作には、コモン、ロバート・グラスパー、クリス・デイヴらが参加。レディオヘッドやビョークからフェラ・クティ、フリート・フォクシーズまで、幅広い音楽を愛聴する彼らしく、雑多なエレメントが交錯する多面的な作品となっている。自らリード・ヴォーカルを取るという新機軸もあり、転機となる作品と言えよう。
ビヨンセ、ジェイ・Z、エミネム、ディアンジェロ、キース・リチャーズらと共演/録音歴のある、LA在住のトランペッターのソロ作。「愛、平和、理解」といったテーマを彼なりに咀嚼した本作には、コモン、ロバート・グラスパー、クリス・デイヴらが参加。レディオヘッドやビョークからフェラ・クティ、フリート・フォクシーズまで、幅広い音楽を愛聴する彼らしく、雑多なエレメントが交錯する多面的な作品となっている。自らリード・ヴォーカルを取るという新機軸もあり、転機となる作品と言えよう。
Liana Flores/Flower Of the Soul
 英国人の父とブラジル人の母を持つ、ロンドン拠点のシンガー・ソングライターの初メジャー作。ジャズを根っこに持ちながら、ボサノヴァなどブラジル音楽の滋養も吸収した音楽性が特徴で、曲によってはジョニ・ミッチェルやベッカ・スティーヴンを思わせるところも。坂本龍一とも交流の深かったチェロ奏者、ジャキス・モレレンバウムも参加しており、ストリングスの格調高い響きが彩りを添えている。アンニュイな雰囲気でささやくように声を発するフローレスのヴォーカルは得難い個性だ。
英国人の父とブラジル人の母を持つ、ロンドン拠点のシンガー・ソングライターの初メジャー作。ジャズを根っこに持ちながら、ボサノヴァなどブラジル音楽の滋養も吸収した音楽性が特徴で、曲によってはジョニ・ミッチェルやベッカ・スティーヴンを思わせるところも。坂本龍一とも交流の深かったチェロ奏者、ジャキス・モレレンバウムも参加しており、ストリングスの格調高い響きが彩りを添えている。アンニュイな雰囲気でささやくように声を発するフローレスのヴォーカルは得難い個性だ。
M.T.B./Solid Jackson
 ブラッド・メルドー(p)、マーク・ターナー(ts)、ピーター・バーンスタイン(g)という3人が30年ぶりに集結してアルバムをリリース。メルドーのトリオを支えるラリー・グレナディア(b)、そのグレナディアとリズム隊を組むこともあるビル・スチュワート(ds)が参加し、けれん味のない、コンテンポラリー・ジャズの旨味を凝縮したような演奏を聴かせる。久々に聴いたバーンスタインのギターに思わぬ成長ぶりを感じたり、ウェイン・ショーターの曲でのターナーのソロに驚嘆した。
ブラッド・メルドー(p)、マーク・ターナー(ts)、ピーター・バーンスタイン(g)という3人が30年ぶりに集結してアルバムをリリース。メルドーのトリオを支えるラリー・グレナディア(b)、そのグレナディアとリズム隊を組むこともあるビル・スチュワート(ds)が参加し、けれん味のない、コンテンポラリー・ジャズの旨味を凝縮したような演奏を聴かせる。久々に聴いたバーンスタインのギターに思わぬ成長ぶりを感じたり、ウェイン・ショーターの曲でのターナーのソロに驚嘆した。
Mark Guiliana/MARK
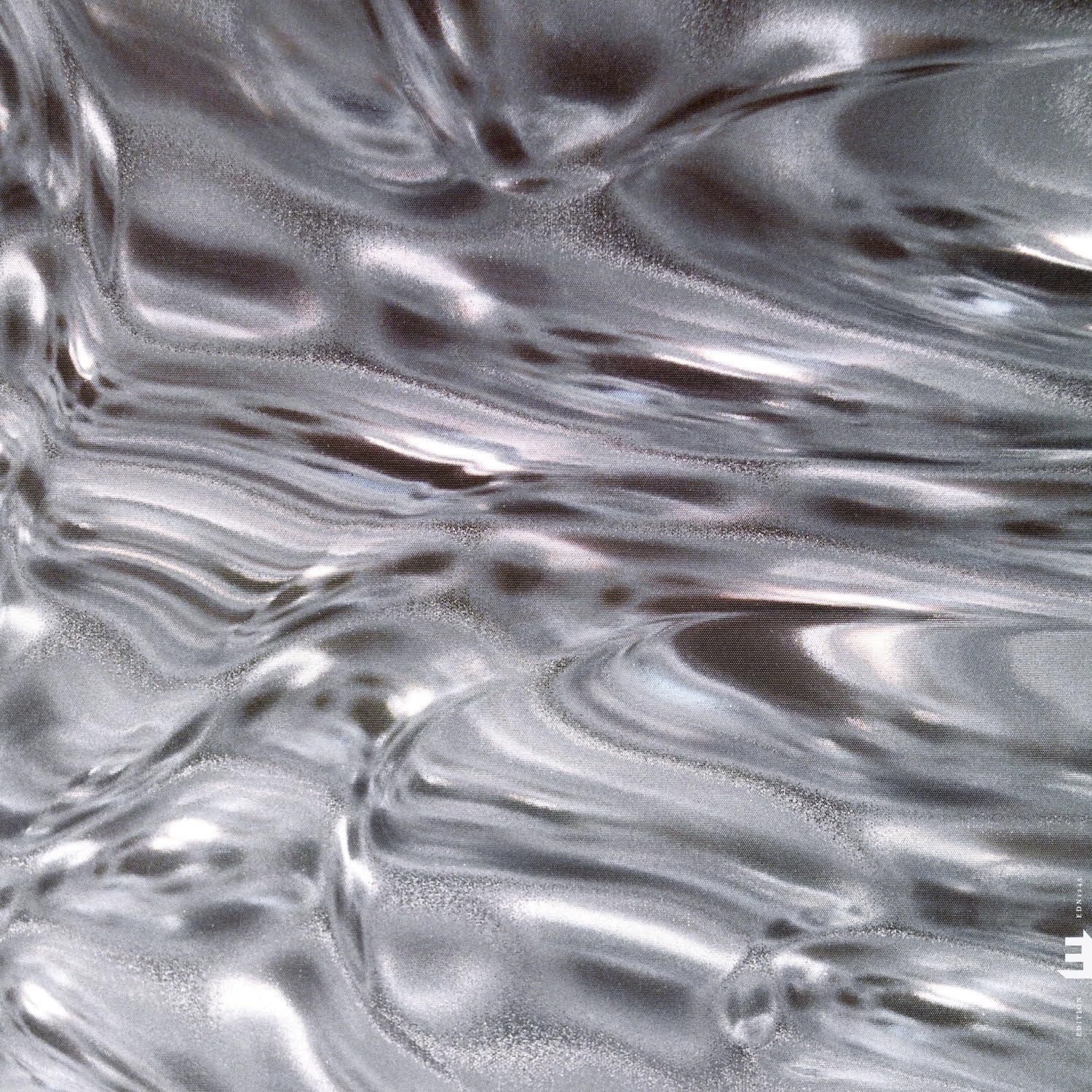 ブラッド・メルドーとのメリアナでも活躍するドラマーの新作は、マリンバ、ヴィブラフォン、パーカッション、チェレスタ、メロトロン、シンセサイザー、エレクトロニクスなどすべての楽器を自ら操ったアルバム。富樫雅彦の不朽の名作『リングス』、あるいは音響派/ポスト・ロックにも通じるサウンド・テクスチャーが魅惑的で、トライバルなビートにも胸躍る。ビート・ミュージックやジャズのプロジェクトで培ってきた経験をすべて投入したような、総決算かつ集大成的な趣もある。
ブラッド・メルドーとのメリアナでも活躍するドラマーの新作は、マリンバ、ヴィブラフォン、パーカッション、チェレスタ、メロトロン、シンセサイザー、エレクトロニクスなどすべての楽器を自ら操ったアルバム。富樫雅彦の不朽の名作『リングス』、あるいは音響派/ポスト・ロックにも通じるサウンド・テクスチャーが魅惑的で、トライバルなビートにも胸躍る。ビート・ミュージックやジャズのプロジェクトで培ってきた経験をすべて投入したような、総決算かつ集大成的な趣もある。
Marty Holoubek/Trio Ⅱ:2
 オーストラリア出身で、2018年から東京を拠点に活動するベーシストのリーダー作。ギターに井上銘、ドラムに石若駿という俊英ふたりを迎え、ヴァーサタイルで予測不可能な旋回を繰り返す。数々のセッションをこなしてきただけあって、マーティーはその場に応じた柔軟なプレイで応じる。骨太で軋むようなベースも彼の個性だろう。CRCK/LCKSでも活躍する井上の縦横無尽なソロ、リムショットを効果的に使う石若のドラムも飛ばしまくる。マーティーの日本のジャズ界への貢献度は計り知れない。
オーストラリア出身で、2018年から東京を拠点に活動するベーシストのリーダー作。ギターに井上銘、ドラムに石若駿という俊英ふたりを迎え、ヴァーサタイルで予測不可能な旋回を繰り返す。数々のセッションをこなしてきただけあって、マーティーはその場に応じた柔軟なプレイで応じる。骨太で軋むようなベースも彼の個性だろう。CRCK/LCKSでも活躍する井上の縦横無尽なソロ、リムショットを効果的に使う石若のドラムも飛ばしまくる。マーティーの日本のジャズ界への貢献度は計り知れない。
Mary Halvorson/Cloudward
 ビル・フリゼールやジュリアン・ラージがそうであるように、ジャズ・ギターは今後、メアリー・ハルヴァーソン以前/以降で区切られるかもしれない——そんな妄想すら浮かぶ才人のアルバム。ギター、トロンボーン、ヴィブラフォン、ベース、ドラムという編成で、前衛的かつ謎めいたサウンドは過去同様だが、以前よりも個々のプレイヤーの裁量に委ねた割合が増えた印象だ。作曲家としての彼女の才覚がより前面に出た感触も。
ビル・フリゼールやジュリアン・ラージがそうであるように、ジャズ・ギターは今後、メアリー・ハルヴァーソン以前/以降で区切られるかもしれない——そんな妄想すら浮かぶ才人のアルバム。ギター、トロンボーン、ヴィブラフォン、ベース、ドラムという編成で、前衛的かつ謎めいたサウンドは過去同様だが、以前よりも個々のプレイヤーの裁量に委ねた割合が増えた印象だ。作曲家としての彼女の才覚がより前面に出た感触も。
Mikael Mani/Guitar Poerty
 アイスランド出身で95生まれのギタリストのギター・ソロ作。ギブソンのフル・アコースティック・ギターを使用して、繊細で柔らかな旋律を奏でてゆく。北欧ジャズの伝統を継ぐようなフォーク・ソング風から、ジュリアン・ラージやビル・フリゼールにも通じるアメリカーナ路線まで、そのメロディ・センスは幅広い。オランダのギタリスト、ジェシ・ヴァン・ルーラーに師事した経験の持ち主だそうで、力強く温かみのあるタッチは彼譲りなのかも。まだ未知数の部分もあるが、それも込みで期待の新人と言えよう。
アイスランド出身で95生まれのギタリストのギター・ソロ作。ギブソンのフル・アコースティック・ギターを使用して、繊細で柔らかな旋律を奏でてゆく。北欧ジャズの伝統を継ぐようなフォーク・ソング風から、ジュリアン・ラージやビル・フリゼールにも通じるアメリカーナ路線まで、そのメロディ・センスは幅広い。オランダのギタリスト、ジェシ・ヴァン・ルーラーに師事した経験の持ち主だそうで、力強く温かみのあるタッチは彼譲りなのかも。まだ未知数の部分もあるが、それも込みで期待の新人と言えよう。
Nala Sinephro/Endlessness
 ベルギー出身でハープとシンセサイザーを操るナラ・シネフロの2作目は、サックス奏者のヌバイア・ガルシア、エズラ・コレクティヴのジェイムス・モリソンが参加。エレクトロニック・ミュージックに括られてもおかしくない作風だが、アンビエントとジャズを統合したような淡くくすんだトーンや、参加メンバーの顔ぶれからジャズの変異体としても捉えられるだろう。フィールド・レコーディングを交えた音の重ね方は実に練られており、ひとつひとつの音を繊細に扱っていることが伝わってくる。
ベルギー出身でハープとシンセサイザーを操るナラ・シネフロの2作目は、サックス奏者のヌバイア・ガルシア、エズラ・コレクティヴのジェイムス・モリソンが参加。エレクトロニック・ミュージックに括られてもおかしくない作風だが、アンビエントとジャズを統合したような淡くくすんだトーンや、参加メンバーの顔ぶれからジャズの変異体としても捉えられるだろう。フィールド・レコーディングを交えた音の重ね方は実に練られており、ひとつひとつの音を繊細に扱っていることが伝わってくる。
Nir Felder/Ⅲ
 越境するジャズ・ギタリストの代表格のひとりであるニア・フェルダーのアルバム。トリオ編成を基本としながらも、マンドリンやバンジョー、シタール、シンセサイザー、MPCなども使用し、多重録音によりつくりあげられている。また、本人はこれまでの作品で最も奔放かつ豪快にギター・ソロを弾きまくっており、手持ちの札をすべて出し切ってしまうように、惜しみなく自らの音楽的ヴォキャブラリーを駆使したプレイは特筆に値する。歪みの効きまくった音色もひたすら心地よい。
越境するジャズ・ギタリストの代表格のひとりであるニア・フェルダーのアルバム。トリオ編成を基本としながらも、マンドリンやバンジョー、シタール、シンセサイザー、MPCなども使用し、多重録音によりつくりあげられている。また、本人はこれまでの作品で最も奔放かつ豪快にギター・ソロを弾きまくっており、手持ちの札をすべて出し切ってしまうように、惜しみなく自らの音楽的ヴォキャブラリーを駆使したプレイは特筆に値する。歪みの効きまくった音色もひたすら心地よい。
Nitai Herskovits /Call on the old wise
 モロッコ人の母とポーランド人の父を持つピアニストのピアノ・ソロ・アルバム。以前からホロヴィッツやリヒテルなどクラシック/現代音楽からの影響を垣間見せていた彼だが、本作ではラヴェルやドビュッシーの影も見え隠れする。抑制の効いたタッチと物憂げなリリシズムが支配する音世界は、ラフマニノフやスクリャービンを愛好する彼の嗜好を直截に反映している。その意味で、ECMから出るべくして出た作品。
モロッコ人の母とポーランド人の父を持つピアニストのピアノ・ソロ・アルバム。以前からホロヴィッツやリヒテルなどクラシック/現代音楽からの影響を垣間見せていた彼だが、本作ではラヴェルやドビュッシーの影も見え隠れする。抑制の効いたタッチと物憂げなリリシズムが支配する音世界は、ラフマニノフやスクリャービンを愛好する彼の嗜好を直截に反映している。その意味で、ECMから出るべくして出た作品。
Norma Winstone, Kit Downes/Outpost of Dreams
 英国のジャズ界を代表するベテランの女性ヴォーカリストのノーマ・ウィンストンが、18年にECMからデビューしたピアニストのキッド・ダウンズと組んだアルバム。80歳という年齢の重みからくるであろう余裕と貫禄を漂わせるノーマのヴォーカルがまず素晴らしい。澄み切った歌声と作為のない節回しは彼女にしかない圧倒的な個性だろう。ダウンズの歌にそっと寄り添うような儚な気なピアノも的確かつパーフェクトなサポートぶりだ。なお、ノーマはアジマスのメンバーとしても活躍中である。
英国のジャズ界を代表するベテランの女性ヴォーカリストのノーマ・ウィンストンが、18年にECMからデビューしたピアニストのキッド・ダウンズと組んだアルバム。80歳という年齢の重みからくるであろう余裕と貫禄を漂わせるノーマのヴォーカルがまず素晴らしい。澄み切った歌声と作為のない節回しは彼女にしかない圧倒的な個性だろう。ダウンズの歌にそっと寄り添うような儚な気なピアノも的確かつパーフェクトなサポートぶりだ。なお、ノーマはアジマスのメンバーとしても活躍中である。
Nubiyan Twist/Find Your Flame
 女性ヴォーカルを含むUKの10人編成バンドの4枚目となるアルバムは、アシッド・ジャズを現代の感覚でアップグレードしたようなダンサブルで軽妙な作風だ。シックのナイル・ロジャースが参加したディスコ・チューンから、フェラ・クティの息子であるシェウン・クティが加わるアフロビートなどが特に目玉だが、しなやかなグルーヴと大所帯ならではの活気が通奏音となっている。いかにもライヴ映えしそうなサウンドだから、大型フェスへの出演が期待される。
女性ヴォーカルを含むUKの10人編成バンドの4枚目となるアルバムは、アシッド・ジャズを現代の感覚でアップグレードしたようなダンサブルで軽妙な作風だ。シックのナイル・ロジャースが参加したディスコ・チューンから、フェラ・クティの息子であるシェウン・クティが加わるアフロビートなどが特に目玉だが、しなやかなグルーヴと大所帯ならではの活気が通奏音となっている。いかにもライヴ映えしそうなサウンドだから、大型フェスへの出演が期待される。
Nubya Garcia/Odyssey
 UKジャズを基軸としながらも、リミックス・アルバムもリリースする女性サックス奏者の2作目。本人の編曲によるオーケストレーションが際立って素晴らしく、ストリングスの典雅な調べに陶然とさせられる。エスペランサ・スポルディング、リッチー・セイヴライト、ジョージア・アン・マルドロウのヴォーカルもフィーチャーされており、ジャズ・ヴォーカルとしては本年度を代表する作品のひとつと言っても過言ではないだろう。力感に富むドラムが推進力となっているのもポイントだ。
UKジャズを基軸としながらも、リミックス・アルバムもリリースする女性サックス奏者の2作目。本人の編曲によるオーケストレーションが際立って素晴らしく、ストリングスの典雅な調べに陶然とさせられる。エスペランサ・スポルディング、リッチー・セイヴライト、ジョージア・アン・マルドロウのヴォーカルもフィーチャーされており、ジャズ・ヴォーカルとしては本年度を代表する作品のひとつと言っても過言ではないだろう。力感に富むドラムが推進力となっているのもポイントだ。
Out Of/Into
 メモリアルなグループのモニュメンタルな作品である。メンバーは、イマニュエル・ウィルキンス(as)、ジョエル・ロス(vib)、ジェラルド・クレイトン(p)、マット・ブリューワー(b)、ケンドリック・スコット(ds)。同レーベル85周年を記念して設立されたこのプロジェクトは、多数のライヴを経て鍛錬を重ねてきた。それゆえ本作は、即興のスリルと作曲の奥深さを併せ持つ、今様ジャズの集大成のようなアルバムとなっている。まさに今のブルーノートの尖鋭性を堂々と提示したような力作だと思う。
メモリアルなグループのモニュメンタルな作品である。メンバーは、イマニュエル・ウィルキンス(as)、ジョエル・ロス(vib)、ジェラルド・クレイトン(p)、マット・ブリューワー(b)、ケンドリック・スコット(ds)。同レーベル85周年を記念して設立されたこのプロジェクトは、多数のライヴを経て鍛錬を重ねてきた。それゆえ本作は、即興のスリルと作曲の奥深さを併せ持つ、今様ジャズの集大成のようなアルバムとなっている。まさに今のブルーノートの尖鋭性を堂々と提示したような力作だと思う。
小曽根真No Name Horses/Day1
 日本を代表するピアニストの主宰するビッグ・バンドの20周年記念盤。サド・ジョーンズやドン・エリス、デューク・エリントンなどの流儀を援用したような賑やかで愉快な演奏が繰り広げられており、新たに加入した若いミュージシャンたちも臆することなく気を吐く。小曽根のコンポーザ―/アレンジャーとしての底力を思い知らされた思いである。緻密なオーケストレーションの妙はもちろんのこと、各プレイヤーのイキのいいソロも聴き応えがある。特にサックス勢の奮闘ぶりが光る。
日本を代表するピアニストの主宰するビッグ・バンドの20周年記念盤。サド・ジョーンズやドン・エリス、デューク・エリントンなどの流儀を援用したような賑やかで愉快な演奏が繰り広げられており、新たに加入した若いミュージシャンたちも臆することなく気を吐く。小曽根のコンポーザ―/アレンジャーとしての底力を思い知らされた思いである。緻密なオーケストレーションの妙はもちろんのこと、各プレイヤーのイキのいいソロも聴き応えがある。特にサックス勢の奮闘ぶりが光る。
Ryan keberle&Catharsis/Music Is Connection
 マリア・シュナイダーのオーケストラに15年以上在籍するトロンボーン奏者のリーダー作。シャイ・マエストロ・トリオのメンバーでもあるホルヘ・ローデル(b)、チリ出身のカミラ・メサ(g,vo)、エリック・ドゥーブ(ds)というカルテット編成で、オリジナルの他、ビクトル・ハラやミルトン・ナシメントの曲を演奏。メサのギターとヴォーカルが中軸を成すが、調和と均衡のとれた端正なオーケストレーションにも耳を奪われる。豊かな曲想と湧き出るアイディアが惜しみなく投げ込まれている。
マリア・シュナイダーのオーケストラに15年以上在籍するトロンボーン奏者のリーダー作。シャイ・マエストロ・トリオのメンバーでもあるホルヘ・ローデル(b)、チリ出身のカミラ・メサ(g,vo)、エリック・ドゥーブ(ds)というカルテット編成で、オリジナルの他、ビクトル・ハラやミルトン・ナシメントの曲を演奏。メサのギターとヴォーカルが中軸を成すが、調和と均衡のとれた端正なオーケストレーションにも耳を奪われる。豊かな曲想と湧き出るアイディアが惜しみなく投げ込まれている。
Samara Joy/Portrait
 実力派というか本格派というか正統派というか。バリー・ハリスをメンターとし、2年連続でグラミー賞を授賞したジャズ・ヴォーカリストのアルバムは、繊細さと力強さが同居する力作。スキャットも交えたヴォーカルはメジャー2作目にして既に堂に入っている。ニュージャージーのヴァン・ゲルダー・スタジオで録音され、チャールズ・ミンガス「ラヴバードの蘇生」などもとりあげる。表現力の豊かさと歌声の説得力は、もはやノラ・ジョーンズにも比肩するのではないだろうかという水準。
実力派というか本格派というか正統派というか。バリー・ハリスをメンターとし、2年連続でグラミー賞を授賞したジャズ・ヴォーカリストのアルバムは、繊細さと力強さが同居する力作。スキャットも交えたヴォーカルはメジャー2作目にして既に堂に入っている。ニュージャージーのヴァン・ゲルダー・スタジオで録音され、チャールズ・ミンガス「ラヴバードの蘇生」などもとりあげる。表現力の豊かさと歌声の説得力は、もはやノラ・ジョーンズにも比肩するのではないだろうかという水準。
Sharada Shashidhara/Soft Echoes
 カルロス・ニーニョやジャメル・ディーンとコラボレーションしたことのあるLAの女性シンガー、シャラダ・シャシダールによる初のリーダー作。ソロ作も素晴らしかったジュリアス・ロドリゲス(p,key)、アンナ・バターズ(b)らを迎え、自らのルーツであるインドの古典音楽やアンビエントの要素を含む演奏を聴かせる。歌と伴奏の関係は曖昧で、両者の区分が溶け合ったような混沌としたサウンドが本作のキモだろう。コケティッシュでチャーミングなヴォーカルも実に魅力的に響く。
カルロス・ニーニョやジャメル・ディーンとコラボレーションしたことのあるLAの女性シンガー、シャラダ・シャシダールによる初のリーダー作。ソロ作も素晴らしかったジュリアス・ロドリゲス(p,key)、アンナ・バターズ(b)らを迎え、自らのルーツであるインドの古典音楽やアンビエントの要素を含む演奏を聴かせる。歌と伴奏の関係は曖昧で、両者の区分が溶け合ったような混沌としたサウンドが本作のキモだろう。コケティッシュでチャーミングなヴォーカルも実に魅力的に響く。
SML/Small Medium Large
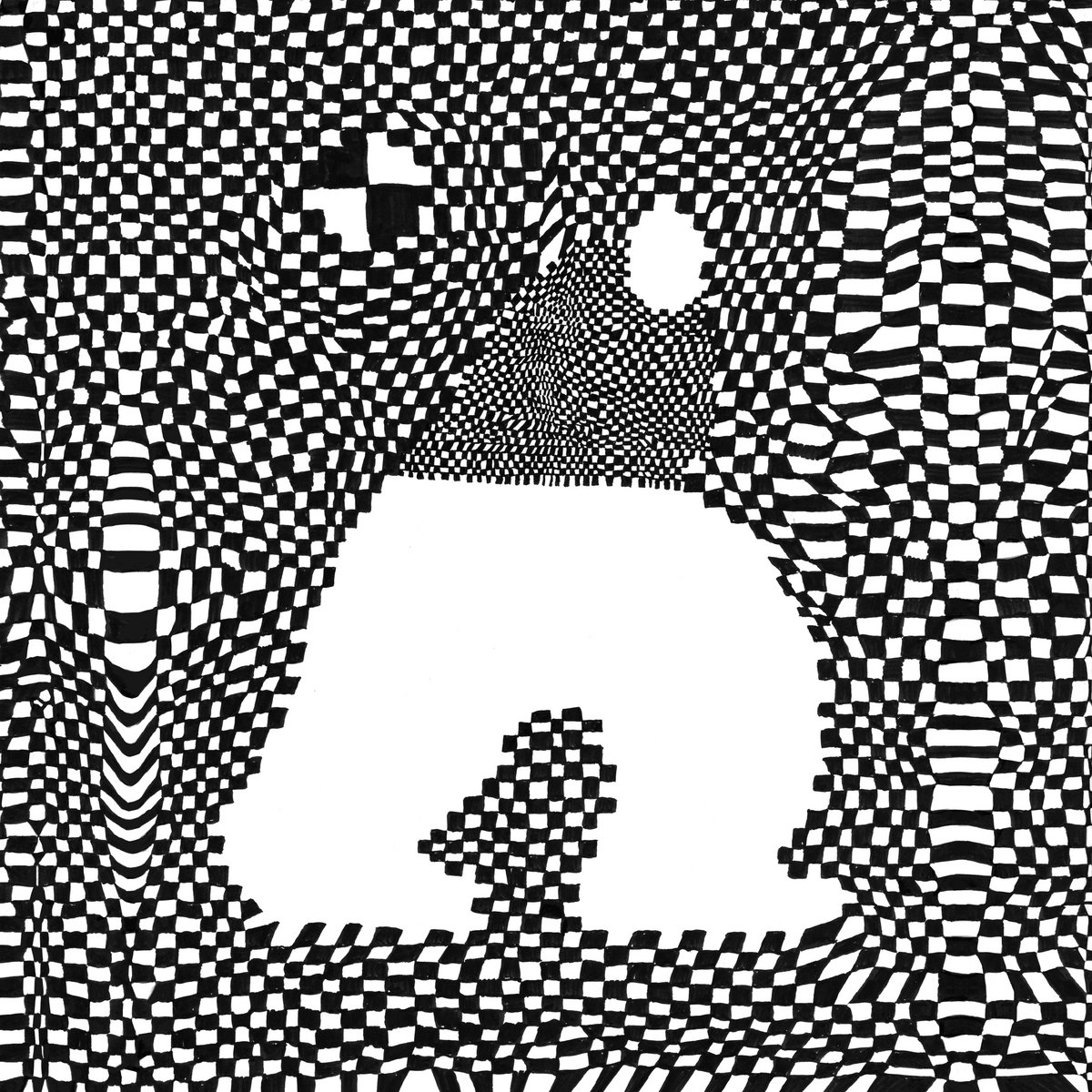 ミシェル・ンデゲオチェロのアルバムをプロデュースしたシカゴ人脈のサックス奏者、ジョシュ・ジョンソンらによるカルテットの初作。アンビエントとジャズとドリーム・ポップを累乗したようなサウンドは、幻惑的でミステリアスだ。サウンドデザインも独創的で、奥行きと立体感のある音像を築き上げている。ジョン・ハッセルなど北欧のジャズに通じる部分もあるが、紛れもないオリジナリティを有しているのは疑いようがない。末恐ろしいポテンシャルを秘めており、今後が楽しみなグループである。
ミシェル・ンデゲオチェロのアルバムをプロデュースしたシカゴ人脈のサックス奏者、ジョシュ・ジョンソンらによるカルテットの初作。アンビエントとジャズとドリーム・ポップを累乗したようなサウンドは、幻惑的でミステリアスだ。サウンドデザインも独創的で、奥行きと立体感のある音像を築き上げている。ジョン・ハッセルなど北欧のジャズに通じる部分もあるが、紛れもないオリジナリティを有しているのは疑いようがない。末恐ろしいポテンシャルを秘めており、今後が楽しみなグループである。
田村夏樹&ジム・ブラック/NatJim
 片や、藤井郷子との度重なる共演で知られ、灰野敬二との共演作も控えているトランペット奏者の田村夏樹。片や、ネルス・クラインからピーター・エヴァンス、マーク・ドレッサーまで数々の共演をこなすジム・ブラック。両者の共演盤は驚くべき成果をあげている。独自の音楽的ヴォキャブラリーを駆使し、手数の多いドラムで迫るジムと、悠然と我が道を行く田村のラッパの相性はかなりいい。アルバム一枚の中で自然と起伏や抑揚が生まれており、ふたりのプレイヤーとしての尖った部分が表出している印象だ。
片や、藤井郷子との度重なる共演で知られ、灰野敬二との共演作も控えているトランペット奏者の田村夏樹。片や、ネルス・クラインからピーター・エヴァンス、マーク・ドレッサーまで数々の共演をこなすジム・ブラック。両者の共演盤は驚くべき成果をあげている。独自の音楽的ヴォキャブラリーを駆使し、手数の多いドラムで迫るジムと、悠然と我が道を行く田村のラッパの相性はかなりいい。アルバム一枚の中で自然と起伏や抑揚が生まれており、ふたりのプレイヤーとしての尖った部分が表出している印象だ。
Terrace Martin/Nintindo Soul
 LAの音楽シーンを代表するひとりでプロデューサー/多楽器奏者のアルバムは、ジャズのほかにネオ・ソウルやR&Bを核としたスムースで耳疲れしないサウンドが特徴。ナインス・ワンダー、コーシャス・クレイらをゲストに迎え、ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンらと組んだディナー・パーティーにも通じる世界が展開されている。ヴォーカルはヌケが良くベースラインはややこもり気味で、ブレイクビーツはラグドな響きでと、音響面でも充実した成果をあげている印象だ。
LAの音楽シーンを代表するひとりでプロデューサー/多楽器奏者のアルバムは、ジャズのほかにネオ・ソウルやR&Bを核としたスムースで耳疲れしないサウンドが特徴。ナインス・ワンダー、コーシャス・クレイらをゲストに迎え、ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンらと組んだディナー・パーティーにも通じる世界が展開されている。ヴォーカルはヌケが良くベースラインはややこもり気味で、ブレイクビーツはラグドな響きでと、音響面でも充実した成果をあげている印象だ。
The Messthetics and James Brandon Lewis/The Messthetics and James Brandon Lewis
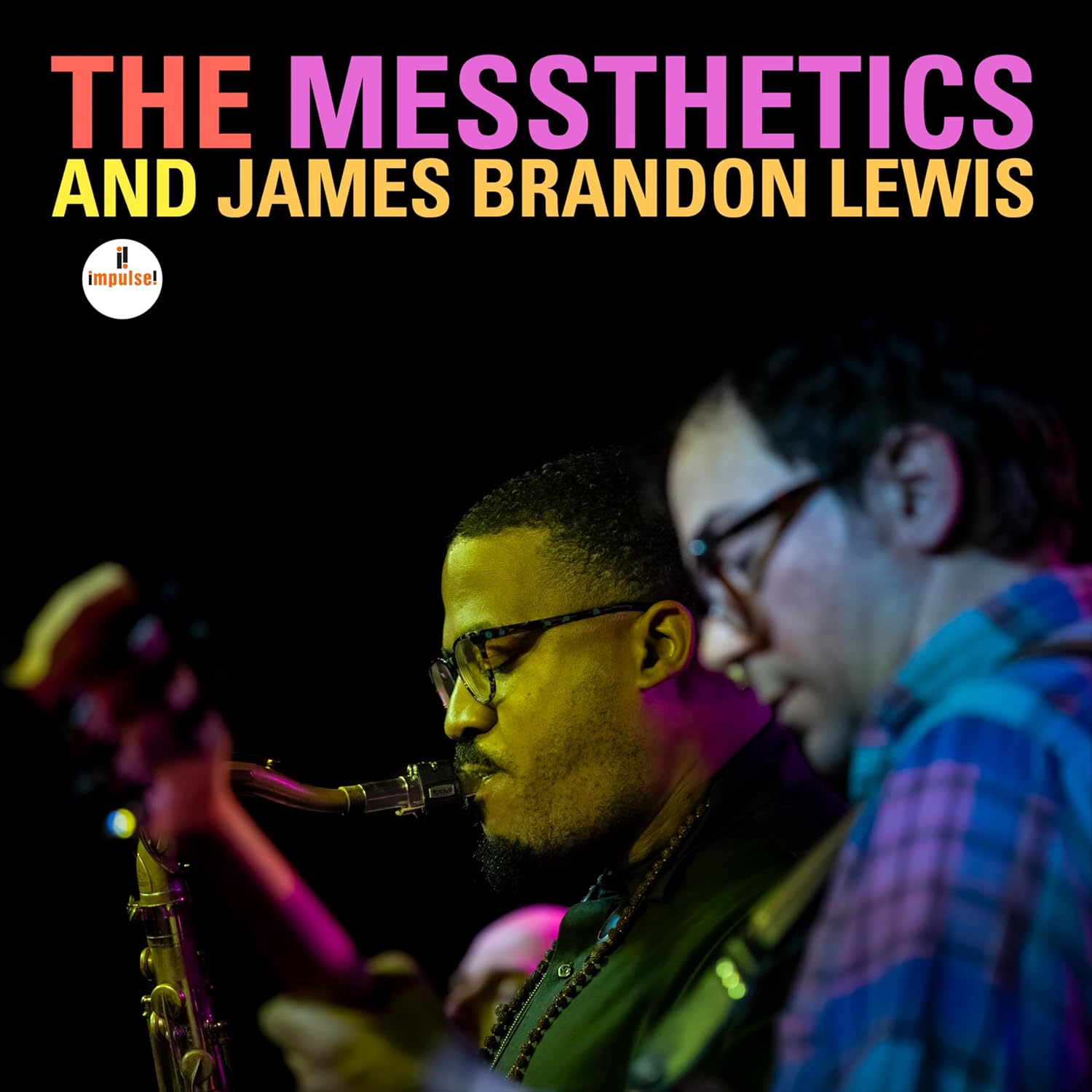 フガジのメンバー3名を擁するエクスペリメンタル・ジャズ・パンク・トリオ、ザ・メステティックス。彼らが、剛腕サックス奏者のジェームス・ブランドン・ルイスと組んだ共演作。リリースは名門インパルスからだ。ハードコア・パンクとフリー・ジャズの融合といった趣のサウンドで、ジェイムスの野趣に富むサックスとディストーションの効いたギターが絡み、混沌とした音像を構築。マーク・リーボウのセラミック・ドッグに通じるヘヴィネスが堪能できる、重厚な演奏が詰まっている。
フガジのメンバー3名を擁するエクスペリメンタル・ジャズ・パンク・トリオ、ザ・メステティックス。彼らが、剛腕サックス奏者のジェームス・ブランドン・ルイスと組んだ共演作。リリースは名門インパルスからだ。ハードコア・パンクとフリー・ジャズの融合といった趣のサウンドで、ジェイムスの野趣に富むサックスとディストーションの効いたギターが絡み、混沌とした音像を構築。マーク・リーボウのセラミック・ドッグに通じるヘヴィネスが堪能できる、重厚な演奏が詰まっている。
Tigran Hamasyan/The Bird Of A Thousand Voices
 故郷アルメニアの音楽を掘り下げ続けてきたハマシアンらしく、本作もアルメニアの民話に触発されてつくられたという壮大な音絵巻である。ジャズ、プログレ、民俗音楽、オルタナティヴ・ロックなどの成分を煮詰めたようなサウンドはヘヴィそのもの。鉛のような重厚感がともなうリズム隊と、ハマシアンの荘厳で幽玄なピアノ、女声ヴォーカルなどがあいまって、ゴシック色も滲む異世界を現出させている。架空の神話を読んでいるような気分にさせられる、面妖で怪しげなサウンドが1時間31分続く。
故郷アルメニアの音楽を掘り下げ続けてきたハマシアンらしく、本作もアルメニアの民話に触発されてつくられたという壮大な音絵巻である。ジャズ、プログレ、民俗音楽、オルタナティヴ・ロックなどの成分を煮詰めたようなサウンドはヘヴィそのもの。鉛のような重厚感がともなうリズム隊と、ハマシアンの荘厳で幽玄なピアノ、女声ヴォーカルなどがあいまって、ゴシック色も滲む異世界を現出させている。架空の神話を読んでいるような気分にさせられる、面妖で怪しげなサウンドが1時間31分続く。
Tyshawn Sorey/The Susceptible Now
 ヴィジェイ・アイヤーらとの共演で名を馳せるタイショーン・ソーリー(ds)のリーダー作。アーロン・ディール(p)、ハリシュ・ラガヴァン(b)とのトリオ編成で、マッコイ・タイナ―、チャーリー・ミンガス、ブラッド・メルドーらの曲から成る。どの曲も15分以上あり、抽象度の高い演奏が続くが、いずれも粘り強く付き合えば曰く言い難い快楽をもたらしてくれるだろう。音数は少なく派手な展開やキャッチーなフレーズも少ないが、現代のピアノ・トリオの理想型と言える硬派演奏ではないだろうか。
ヴィジェイ・アイヤーらとの共演で名を馳せるタイショーン・ソーリー(ds)のリーダー作。アーロン・ディール(p)、ハリシュ・ラガヴァン(b)とのトリオ編成で、マッコイ・タイナ―、チャーリー・ミンガス、ブラッド・メルドーらの曲から成る。どの曲も15分以上あり、抽象度の高い演奏が続くが、いずれも粘り強く付き合えば曰く言い難い快楽をもたらしてくれるだろう。音数は少なく派手な展開やキャッチーなフレーズも少ないが、現代のピアノ・トリオの理想型と言える硬派演奏ではないだろうか。
Vijay Iyer/ Compassion
 物理学の博士号を持つインド系ピアニストが、中国ルーツのリンダ・メイ・ハン・オー(double-b) 、アイヤーが「今地球上にいる最高の音楽家」と称賛するタイショーン・ソーリー(ds)とのトリオで放つ2作目。武骨さと繊細さを併せ持つリズム隊と、慎ましさと大胆さが共存するアイヤーのピアノが拮抗し、知的にコントロールされたサウンドを創出している。聴く度に新しい発見と驚きが待っている、創意あふれる一枚。
物理学の博士号を持つインド系ピアニストが、中国ルーツのリンダ・メイ・ハン・オー(double-b) 、アイヤーが「今地球上にいる最高の音楽家」と称賛するタイショーン・ソーリー(ds)とのトリオで放つ2作目。武骨さと繊細さを併せ持つリズム隊と、慎ましさと大胆さが共存するアイヤーのピアノが拮抗し、知的にコントロールされたサウンドを創出している。聴く度に新しい発見と驚きが待っている、創意あふれる一枚。







